「レイヴンを守るためって……リタ、どういうことなの? だってアレクセイは……」
カロルは言い淀んだ。
御剣の階(みつるぎのきざはし)のてっぺんでも、ザウデの最深部でも、アレクセイはレイヴンに語りかけている。
おまえは道具だと。道具にしかすぎないのだと。
「心臓魔導器は、きちんと計算された上で作られているってことよ」
リタの返答を聞きながらも、ユーリは別の疑問を口にした。
「レイヴンは体への負担を感じていたんだろ? 痛みがあるなら…」
守るというのはおかしいのではないか。
「痛みが無かったら、ムチャして余計命を縮めてたわね」
痛みは心臓が発する警告。
「まあ、そりゃそうだな」
「ユーリの言うことはもっともなのよ。イヤな言葉だけど、「道具」として使うならこんなに繊細なシステムにしない」
リタは眉間にしわを寄せた。
「あたしがあの結論に達した理由の一つではあるわ。システムを繊細に作っておきながら、それを守る筺体は恐ろしく頑丈に出来てる。でなきゃ、ユーリの剣を受けて生きてるなんて考えられない」
バグティオン神殿での死闘のさなか、シュヴァーンは不意に剣を下ろした。ユーリの刃は彼の胸を切り、切り裂かれた服の間から、心臓魔導器の存在を知った。
だが、裏を返せば、ユーリの刃を、魔導器が跳ね返したことになる。
「信じられないくらい硬い素材で作られているのは確かだわ」
リタが何を言いたいのか、ユーリは分かった。
「おっさんの心臓は、それだけじゃないんだな?」
「アレクセイが定期的にメンテナンスをしていた……それと何か関係があるのかしら?」
ジュディスの問いにリタは小さくうなずいた。
「この子……たぶん最初はすごく不完全なものだったはずなの。今よりずっと」
ユーリはちらりとレイヴンを伺い見た。やや困ったような笑みを浮かべている。だが、ユーリの目には仮面のように映った。
哀しみも不安も押し隠すための仮面。
(レイヴン……覚悟を決めて俺たちに心臓をさらしたあんたでも、アレクセイと心臓魔導器のこととなると、違う意味を持つのか……?)
表情が陰ったユーリを、エステルは不安げに見上げた。
「不完全……か。そう言われてみれば、そうだったかもね」
無精ヒゲの生えたあごに手をあて、レイヴンは虚空を見上げた。エステルの不安げな視線が、今度はレイヴンへと移る。
リタの声に熱が入った。
「少し戦っても、今より体にかかる負担が大きかったはずなの。アレクセイは、10年前からずっとおっさんの心臓魔導器(カディスブラスティア)を見続けてた……そして、その間もずっと心臓魔導器の研究を続けていたみたいなの」
たたみかけるような口調ながらも、リタは時折レイヴンの様子をうかがっていた。
魔導器(ブラスティア)のことになると全てが見えなくなり、何も考えずに行動する……そんな少女はもう居ない。
旅を通して、リタもまた、確実に成長していた。
似つかわしくない「迷い」の表情を浮かべるリタに、レイヴンが優しく先を促す。
「続けて、続けて」
言葉が自信となったのか、リタはまっすぐレイヴンを見つめた。
「……もちろんあいつの一番の研究目的は、宙の戒典(デインノモス)の複製を作ることだったんだろうけど……同じ魔導器ってこともあったかもしれない。並行して研究していたんだと思う。結果、エアルの代わりに使う生命力を、少しずつ減らすことで、体への負担も減らしていったの」
「何でそう思うんだ?」
いぶかしげなのはユーリだけではなかった。エステルもカロルも、それぞれ不安とも疑問ともつかない表情を浮かべている。
そんな彼らに、リタはゆるぎない口調で返した。
「魔導器は嘘をつかないわ。アレクセイがしてたのは、ただのメンテナンスじゃなかった……常に新しい術式を開発して、魔導器を一番いい状態に更新し続けてた」
「その更新の記録が残っているのね?」
「うん」
ジュディスの言葉に、リタはこくんとうなずく。
「筺体(コンテナ)が大きいのもそう。こんな大きなものを人の体に埋め込むなんて正気の沙汰じゃない。そもそも魔導器に心臓の代わりをさせるなんてこと、あたしなら思い付かないわ。……でも、その場しのぎでやったことじゃないと思う。5年後、10年後を考えて、この子は造られてる」
「最初から、新しい術式をほどこす余地を残して」
リタの言葉をジュディスが補った。
レイヴンがはだけた衣服を整えた。ボタンをはめ、ベルトをしめなおす。
リタの顔が泣きそうになっている……エステルが思わず駆け寄ろうとしたのを、ユーリが制した。
「これは、おっさんとリタの話だ」
「ユーリ……」
エステルはうつむいた。
「そうですね…すみません」
少しだけ、ユーリは笑った。頑固一徹かと思いきや、エステルは自分の非を認め謝る素直さもある。
優しさや他者への労りが、彼女を駆り立て、行動へと移しているのだ。
「謝ることじゃねぇさ」
「…はい」
椅子には戻らず、エステルはユーリの隣に歩み寄り、彼と同じように壁にもたれた。レイヴンとリタが座る長椅子のやや後方、ここからだと横顔しか見えない。
やや伏し目がちのまま、リタはさらに続けた。
「心臓魔導器の初期の状態から考えたら……全部つじつまが合うの。だって、おっさんが……騎士団の隊長が諜報活動をするって、よく考えたらおかしいでしょ」
エステルが答えを求めてユーリを見上げる。
「俺が騎士団に居た期間は短いからな……ただ、隊長っていやどっちかといえば部下に命令する立場だったな」
率先して先頭に立ち、部下の士気をあおることもある。だが、全ての行動は、数百に及ぶ部下を手足のごとく使うために用いられなければならない。そのための「隊長」なのだ。
上に立つものが居ない状態が長引けば、それだけ指揮系統も壊れやすくなる。
本来ならば、「レイヴン」という存在が生まれる必要性は極めて低いはずだった。
「あたしは騎士団がどういう組織かなんて詳しくは分からない。でも、騎士団の隊長が身分を偽ってギルドに潜入する……つまり、長期間帝都を留守にする……そんなのって普通ならありえないって思う……でも……」
伏し目がちだった目が一気に見開く。リタの声に強さが戻る。
「それは全部必要だったのよ!」
「……体の負担を減らすためね?」
各地でヘルメス式の魔導器を壊してまわっていた時、ジュディスは全身を覆うタイプの甲冑を身につけていた。だが、ユーリと出会った直後、脱いでしまった。理由は極めて単純だ。重いので着たまま動けば疲れてしまう、それだけだった。
だが、死線を彷徨い、自らの心臓を失い、人の手で蘇ったシュヴァーンにとっては、騎士の鎧は十分すぎる「枷(かせ)」だったのではないか……ジュディスが何を言いたいのか、ユーリもエステルもカロルも……そしてレイヴンも理解した。
「おっさんに命令したの、アレクセイでしょ?」
架空の存在「レイヴン」を作り上げ、ギルド・ユニオンに入りこむ。「レイヴン」は弓使いで、術も使えるので、接近戦をする必要はない。当然、まだ脆弱であった心臓にかかる負担は少なくてすむ。その上、剣を使わないので、騎士独特の剣術が露呈し身分が暴かれる恐れも減り、結果として、10年も経たぬ間に「天を射る矢(アルトスク)」の幹部にまで上り詰めた。
他方、シュヴァーン隊は一枚岩のように連携の取れた隊に育ち、隊長がたとえ不在であっても、指揮系統が崩れることは皆無という、稀有な一個大隊となった。
すべてがアレクセイの思うとおりに運んだのだ。
レイヴンはぽりぽりと頭をかいた。
「やっぱり天才魔道士少女は違うわ。そこまで詳しく分かっちゃうもんなのね」
「じゃ…」
リタの言葉にレイヴンが自分の言葉を被せる。
「……確かにリハビリだった面はあるかねぇ…。戦争から戻って、突然隊長に抜擢されたはいいが、体がボロボロで登城が遅れてね……就任の儀式も伸び伸びになってて申し訳なかったわー」
「本当に大抜擢だったんだ…」
「カロル先生は、もっとびっくりするべきだな。おっさんより前に平民から隊長になった奴なんていねぇ」
ユーリに向かってレイヴンは片目をつむってみせた。
「フレン君はもっとすごいじゃないの。 平民から騎士団長にまで昇進したヒトって初めてだもの」
ユーリは沈黙した。
ドレイク将軍は言った。騎士団に伝わる秘術を伝えるに値するのはシュヴァーンしかいないと。
アレクセイが死に、シュヴァーンが騎士団から去らなければ、もしかしたら騎士団長は違っていたかもしれない……そのことを一度も考えたことがないといえば嘘になる。
内側から帝国を変えるために、ユーリはフレンとともに騎士団に入った。それは、功績を上げれば平民出であっても地位を得て、発言権を得ることができると信じたからだ。彼らだけではない。平民が多く登用されるようになったのは「シュヴァーン」という前例があったせいなのだ。
ユーリは左手を見つめた。剣を握るその手が覚えている。バグティオン神殿で対峙した時のシュヴァーンの剣の重さと鋭さを。
リタの説明の通りならば、シュヴァーンは深い傷を追い、心臓への負担と戦いながら、長い時間「レイヴン」として過ごしたことになる。剣の技術を磨く時間は限られていたはずだった。
それでもあの時、隊長首席の名が伊達ではないことをユーリたちは知った。
死を覚悟していたとはいえ、尋常ではない剣さばきと、技の応酬。
生ける屍の――己を死人と評した男の振るう剣では、決して無かった。彼が心臓を失う前、どれほどの手練(てだれ)であったのか想像もつかない。
ルブランのいう「人魔戦争を生き抜いた英傑」とは誇張でも何でもなかったのだ。
エステルが一歩前に出た。
「シュヴァーンが隊長に抜擢されたのは、単に人魔戦争から生きて戻ったからではありません。私はそう聞いてます。剣技に優れ、義に厚く、慕う者が多かった……騎士の中の騎士だと」
「えっ、ホントなの、エステル!?」
驚きすぎたカロルが椅子から転げ落ちそうになる。
レイヴンが大袈裟な素振りで手を振り否定した。
「俺様、ホント、誤解されやすいのよね。それにもう……10年も昔の話よ」
本当に姫様にはかなわないとばかりに、レイヴンは肩をすくめた。
「ただ……まあ、譲ちゃんの前では言いたかないけど、大将が俺を「道具」として使いたかったのは事実だろうねぇ。で、使うからには、準備も点検も必要ってことなのよ」
結局は。
口元は笑みの形を作っている。だが、ユーリは知っていた。
アレクセイをクズ野郎だと言った時に、レイヴンは「最初からクズだったわけじゃない」と庇った。重責の中で変わっていってしまったと。
過去を知る彼にとって、アレクセイに「道具」と呼ばれるのは、どんな気持ちだったのか……。
エステルもまた、何か言いたそうではあったが、レイヴンが先に口を開いた。
「まあコレのおかげで、何とかおまえさんらに、ついてってるけどね」
軽く胸を押さえながら、若者は体力が有り余ってるから、一緒に歩くだけでもタイヘンなのよねぇと茶化す。
リタの拳がぶるぶると震えた。
「言いたいのはそれだけ?」
「え? 何でリタっち、突然怒り出したの??」
へらっとした顔に、リタの拳が唸りを上げ叩き込まれる。
「ぐぶぁっ」
鼻を押さえるレイヴンは涙目になっている。
「ちょ……ひどいわ、リタっち! 鼻血出ちゃうじゃない」
「言い方が悪かったわ。「道具」よばわりしてたアレクセイに感謝しろなんて言わない。でも、この子(カディスブラスティア)はおっさんをずっと守ってた。それは事実なの。だから大切にしてほしい……あのバカ騎士団長ですら大事に扱ってたんだから」
息が荒くなるのもかまわず、リタは全ての力を振り絞るようにして、レイヴンに「思い」をぶつけた。
これは命を守るために作られた「魔導器」なのだと。
無くてはならない大切な体の一部であると。
生きているからこそ、自分の体は大事にしなければならないと……。
気圧されたかのように、レイヴンは呆然とリタを見つめた。
カロルがピンときた。
「ユーリの前で剣を下ろしたりしない」
「まだあるぞー。橋のたもとで、たそがれない」
ユーリがわざとらしく棒読みする。
「もう一つあります! 具合が悪かったらすぐにリタに見てもらう!」
笑顔でエステルが続いた。
「じゃー」
魔法が解けたように、レイヴンの顔にも笑みが広がった。
「腹痛になったら、リタっちにお腹さすってもらおうかな♪」
「ふんっ」
すかさず、リタが隣に座るレイヴンの足を思いっきり踏ん付け、ぐりぐりとトドメを刺す。
「ふおおぉぉ」
悶絶するレイヴンを放って、リタは立ちあがった。
「ホントにおっさんはある意味ムチャしすぎよ。あの時だって……」
言いかけてから口をつぐむ。
心臓の力を開放して、巨大な岩を受け止め、崩落する神殿からの脱出口を死守した。
剣を使って戦うだけでも心臓にかかる負担は大きいのに、死を覚悟の上で、「仲間」を、身を呈して庇ったのだ。
「うふふ……泣いていたものね、あなた」
「ちょっと、あんたーー!!!」
顔を真っ赤にして、リタはジュディスに詰め寄った。
レイヴンが驚いたように顔を上げる。
「え? あ、リタっち、泣いてくれたの?」
「ななななな……泣いてなんかないわよ。あんたみたいなバカ見たことないって言ってただけよ!」
「バカ…ですか…」
やっぱり天才魔道士少女はクールだわーと、レイヴンが鼻をずずっとすする。
「まあ、カロル先生は号泣してたからな。安心しろ、おっさん」
「ひどいよ、ユーリ!」
「ふふ。カロルだけじゃないわ。あの時は、あなたも辛そうだったものね?」
ジュディスにほほ笑みかけられ、ユーリは渋面になった。
「…そういや、ジュディが一番落ち着いてたよな…」
「ってことは、ジュディスちゃん……全然哀しくなかったんだ…?」
レイヴンがショックを隠せない様子で、よよよとくずおれた。
「あら、私、胸が張り裂けそうな思いだったわよ?」
「あんたが言うと、何でか嘘っぽいのよね…」
リタが疲れたように、ため息と一緒にこぼした。
「それと、おっさん!」
リタに呼ばれて、レイヴンはあからさまにびくつく。
「な…何かしら?」
「一度死にかけたクセに、ここのところずっとメンテナンスしてなかったせいで、その子、ガタがきてる部分があるわ。今は精霊のおかげでごまかしが効いてるけど、これから計算式を作り上げて」
ビシッとレイヴンの胸を指差した。
「おっさんの心臓魔導器を、アレクセイがやってたよりももっと高度な術式に組み直してあげるから。待ってなさい!」
「いたいけなおっさんを、まだいじるんだ?」
わざとらしくレイヴンが泣く素振りを見せる。
「おっさん、こりゃ、リタの気が済むまで何度でも付き合わされるぞ?」
ユーリがお疲れ様とレイヴンの肩をたたいた。
「えー…?」
レイヴンの眉が八の字になる。だが、その目はどこか、いたずら好きの子供のような輝きがあった。
少なくともユーリにはそう見えた。
「あ、そうそう」
リタは忘れてたわとばかりにレイヴンに再び向き直った。
「さっき見てあげてた時に、その子」とレイヴンの胸を指差す。
「外部からアクセスできないようにしておいたから」
エステルがはっとした。
「世界中の魔導器がネットワークでつながって、すべての魔導器が精霊化しても、おっさんのはそうはならない」
ツンとしてリタは背中を向けた。
「あんた、自分から言わないんだもの。感謝してよね」
レイヴンがふっと笑った。
「ありがとう、リタ」
ギョッとしてリタは振り返った。口調がいつもと違う。これはむしろ…。
「えっ、何よ、俺様何かヘンなこと言った?」
リタはぶんぶんと首を振った。単なる気のせいに違いない。違いないのだ!
「さっ、エステルも、ジュディスも! もう終わったんだから、あたしたちの部屋に戻るわよ!」
「え、リタ? もう、よろしいんです?」
「今日はもう終わりよっ」
リタに腕を引っ張られ、半ば引きずられるようにして、強引にエステルは連れて行かれた。
「まあ、せっかちね」
そう言いながらも、ジュディスはリタの後を追うようにゆっくりと部屋を出る。
「また、明日ね、ジュディスー」
カロルの声にジュディスは軽く手を振ってからドアを閉めた。
「はー、おっさん疲れたわあ」
レイヴンがごろんと長椅子に横たわった。
「おっさんは休んでな。カロル、先にフロ使えよ」
「え、いいの? ありがとう、ユーリ」
バタバタと用意を始める。ユーリはベッドに腰掛け、ラピードの武器を手にとり、丁寧に磨き始めた。
先ほどまでとは違う、静かな空間。
横たわった頬にかすかな温もりが伝わる。先ほどまでリタが座っていた場所。
まったくすごい子だわとレイヴンは苦笑した。
忌むものであったはずの心臓魔導器が、全く違うものになってしまった。
これがレイヴンにとって……シュヴァーンにとってどれだけ大きなことか、彼女は知るよしもないだろう。
胸に手を当てる。心臓魔導器が一定のリズムで鼓動している。
生きている証。
何としてでも「星食み」から世界を救わなければならない。そうレイヴンは思った。
今度こそ「死ぬ気」で頑張れる――もう死人ではないのだから。
--------------------------------------
※基本的に「リタと心臓魔導器」のお話全体と、「アレクセイと心臓魔導器」とが対になります。
話の長さが違いすぎて、全く説得力ないですけど、興味のある方は両方読んでいただけると嬉しいです。
(一部、あえて同じような表現を使ったりしている部分もありますので、その辺もお楽しみください♪)
※魔導器の設定などに関しては、もちろんゲーム本編も参考にしていますが、攻略本掲載のより詳しい世界設定なども参考にしています。(心臓魔導器の設定については完全な捏造です)
↓読まなくてもいい話↓
長くなりすぎるので、アレクセイとレイヴンの関係についてはまた別の話で。
みんながそれぞれどう思っているのか、実際のところは?みたいな感じになるかと。
というか、イエガーとレイヴンがどうしてアレクセイに選ばれたのかとか、
彼らの心臓魔導器についての違い?とか、書きたいことが一杯です。
それよか、この「リタと心臓魔導器」……なんかレイリタ話みたくなってしまった!
あえてカップリング要素はナシで行きたい意向ではありますが、レイリタファンの方はそのように読んでいただいてくださっても、とってもオッケーです♪
◆参考サブイベント……「アレクセイの研究」「レイヴンと心臓魔導器」「騎士団最強の奥義」
◆参考スキット……「どこまでもうさんくさいレイヴン」「ジュディスの鎧」「親衛隊について」
◆参考資料……市販の攻略本の用語集。
※アレクセイの身分については、平民ではなく身分も申し分ないらしい?実際のスキットでは、「先の皇帝陛下の御前試合で優勝して騎士に推挙された」とありますが……騎士団長に推挙されたという方が確かに自然。御前試合というからには、騎士しか参加出来無さそうですから。それにしてもナゾです……。
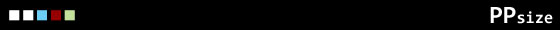
2009.07.10.
|