リタが深紅に輝く魔導器に手をかざすと、フッと空中に「盤」が現れた。レイヴンの胸の、やや上のあたり、光の集合体で構成されたそれは、これまでリタが操作してきた数々の操作盤と大差ない形状をしている。
数十にも及ぶ小さな文字盤の上を、少女の華奢な両手が滑るように動いてゆく。 文字盤の上に浮かび上がる円形の光の中で、リタの指の動きに合わせて、たくさんの文字が生まれては消えていった。
レイヴンは少女を見降ろした。明晰な頭脳とは裏腹に、まだ若干の幼さが残る翡翠色の瞳に、文字盤の光が映り込んで見える。
迷いや怖れはもうない。その目にあるのは、熱意と探究。何があっても、必ずやり遂げるという強い思い。
真剣で、真摯(しんし)なまなざしは、仲間の……レイヴンの体を気遣ってのことだった。
魔導器以外にさしたる興味も抱かず、他人にも無関心。冷めたきった口調と眼差しから、どちらかといえば表情の乏しく見える少女……そんな印象を抱いたのは、いつの頃だったか……。
リタは覚えてないだろうが、騎士団の隊長首席として、また、騎士団長アレクセイの使者として、レイヴンは一度会っている。彼女が10歳で魔導器研究を始め、すぐに頭角を現し、数年で、アスピオいちの頭脳とささやかれるようになった頃だ。
同じアスピオの研究員であるウィチルのことすら、ほとんど記憶に残らないほど、当時からリタは研究に没頭していた。
帝都から訪ねてきた騎士のことなど記憶に無くて当然だろうが、逆にシュヴァーン以下、同行した騎士たちには、強烈な印象を残した。
一つは、研究者というには、あまりに年端もいかない少女であったこと。
ウィチルはリタよりさらに幼いが、そもそもリタやウィチルのように幼少期から研究者の道を歩む方が特殊だった。
もう一つは、地位にも名声にも富にも、何の興味も示さなかったことだ。
すでに、彼女のために貴族街に屋敷も用意していた。貴族と同等の高い地位を約束した上で、魔導器研究の第一人者として招聘(しょうへい)するはずだった。
だが、リタ・モルディオは帝国(結局はアレクセイの独断だったようだが)からの要請を一蹴した。理由としては、帝都では魔導器研究に集中できないからとのことだったが、単に気が乗らなかっただけだろう。
アスビオには帝国魔導器研究所が置かれ、世界中の魔道士たちが集う。そのため帝国の厳重な管理下にあり、一般人の立ち入りも制限されている。アスピオの魔道士は帝国の庇護の元、研究を続けていることもあり、騎士団の要請には応じる義務があった。
それを断ったのである。
リタが天才魔道士少女の名を欲しいままにしていなければ、不問になどならなかっただろう。
それがまあ……とレイヴンは目を細めた。
感情が見えにくく、時に、冷たくさえ見えることのあったその眼差しが、今は沢山の感情を宿し、喜怒哀楽を素直に表している。
変われば変わるもんだ……と彼は思った。それは無論、リタだけではない。
ユーリは旅の間に、やるせなさを抱えた自分自身と向き合い、答えを見つけ出した。
エステリーゼは広い世の中を見分することで、上に立つ者の振る舞いと、救わねばならぬ弱者の間にある溝を知った。
カロルは、怖れる自分に打ち勝ち、溢れる勇気を手に入れた。
リタと同じく、他人に対する興味が薄かったはずのジュディスは、自分の生きる目的を見つめ直した。
そしてレイヴンは………もう一度生きようと思った。
償いとけじめのために、再び仲間たちの元へ戻ったのは事実だ。
だが、今は、心から生きたいと願う。
シュヴァーンの名も、騎士としての栄光も名誉も地位も捨てて、架空の存在であったはずの「レイヴン」として生きる道を選んだ。だが同時に、造りものの心臓に対する不安と、そして、一度死んだはずの自分が、先に死んでいった者たちより長く生きることへの疑問が生じた。
どうしようもない堂々巡り……。
だが、どうしてだろう。
仲間と一緒に過ごす時間が長くなればなるほど、生きていいと思えるようになった。
ごく自然に、生きていることを実感する瞬間があった。
だから、今、こうして、仲間と一緒に、心臓魔導器と向き合っているのかもしれない―。
リタの手が止まった。
空中に浮かんでいた光の「盤」が瞬時に消える。まるで最初からそこに何も無かったかのように。
「……大体分かったわ」
掲げられていたリタの手が、ゆるゆると自身の膝の上に落ちた。
「ああそう! それでどうだったの?」
神妙な面持ちの仲間たちをよそに、レイヴンの明るい声が響いた。
リタはじいっとレイヴンの目をみつめた。唇を引き結び、嘘など許さないっといった強い感情が見て取れる。
「……ねえ、その前にちょっと聞いてもいい? あのバカ騎士団長、定期的におっさん見てたでしょ?」
「え? フレンくんのこと?」
直後、げほっとレイヴンがせき込んだ。裸のままの腹筋に、再びリタの拳が突き刺さる。
「リ……リタっち、さっきと同じとこ、同じとこに2度は反則よ……」
「べっつに痛くはないでしょ! 筋肉ついてんのに!」
「い……痛いです……」
お腹をさするレイヴンに、ユーリが腕組みをしたたまま歩みよる。
「そんなどうしようもないボケかますってことは、あんま、触れてほしくなかったのか」
リタが小さく息を飲んだ。
「ちょっと青年……相変わらずずばっと言うわね」
「おっさんが嫌な話題だったら、俺らは席外すってことだよ」
カロルが椅子から飛び降りた。
「ユーリ……そうだね。ごめんねレイヴン、リタからゆっくり話を聞いてね」
部屋を出て行こうとしたカロルを、レイヴンは再び止めた。
「少ー年ー。違うってば! さっきと同じことやってるじゃないの」
頭をぽりぽりとかきながら、やや恥ずかしそうにカロルはもう一度椅子に座りなおした。
ジュディスが指先を自分の頬にあて、首を軽くかしげる。
「席を外してほしいんなら、リタに見てもらう前に外してもらっている……そういうことかしら?」
「いや、さっっすがジュディスちゃん! 大人の女は違うわぁ……って、まあそーゆーこと」
語尾に軽妙さは無かった。
リタはうつむき、少しだけ沈黙したあと、もう一度レイヴンではなく、彼の心臓魔導器を見つめた。
美しい深紅の鼓動。
「アレクセイは……」
リタの言葉を受け取るように、レイヴンがいつになく落ち着いた口調で続けた。
「大将は、こいつの点検はかかさなかったよ。10年前からずーっと、俺が帝都に戻るたびに……ね」
大いなる秘密。決してあってはならない魔導器。作った者、造られた者、二人きりの室内。
生かされるための儀式……。
口元は笑いの形を作っているのに、リタには彼の心が違う思いに満ちているように見えた。
このこと……言わない方が……ここにいるみんなのためにも、いいかもしれない……でも……。
「ああ、やっぱダメ! エステルも居るし、アレクセイは絶対許せないし、おっさんはイヤかもしれないし、ホントはこんなこと言いたくないけど……」
リタは大きく息を吸い込んだ。
「この子……アレクセイが作った心臓魔導器(カディスブラスティア)……おっさんの体のこと考えて、守るために出来てる……」
--------------------------------------
リタと心臓魔導器4に続きます。
※基本的に「リタと心臓魔導器」のお話全体と、「アレクセイと心臓魔導器」とが対になります。
話の長さが違いすぎて、全く説得力ないですけど、興味のある方は両方読んでいただけると嬉しいです。
(一部、あえて同じような表現を使ったりしている部分もありますので、その辺もお楽しみください♪)
※魔導器の設定などに関しては、もちろんゲーム本編も参考にしていますが、攻略本掲載のより詳しい世界設定なども参考にしています。(心臓魔導器の設定については完全な捏造です)
◆参考スキット……「アレクセイについて」 「リタっていくつ?」 「リタとウィチルは知り合い?」
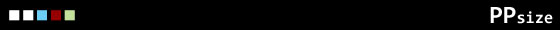
2009.07.04.
|