「レイヴンさん、もし、お嫌でなければ、お願いがあるのですが」
「どったの、フレンちゃん、真面目な顔しちゃって」
タルカロンの塔に入って半日あまり。元市街地のような場所を最初の宿営地に選んだ。テントを張り、それぞれが休憩を取っている。
ごろんと横になっていたレイヴンに、真剣な面持ちで声をかけてきたのはフレンだった。
「僕とお手合せをお願いしたいのです」
やや距離を置いたところから、剣戟の音が聞こえる。ユーリとカロルが手合せしているのだ。
「こんな老体でよければいつでもOKよ。でも、俺様でいいの? ユーリとの方がいくない?」
デュークは魔術も用いるが、基本的には剣術使いだ。空中戦を得意とするジュディスや、パワー型のカロルよりも、剣を使うユーリの方が手合せの相手としては妥当ではないのか……それを暗に示しながらも、レイヴンは片目をつむってみせた。
「まあ、俺様にとっては、若者と手合せ出来るのは、とってもありがたいけどね」
くだけたレイヴンの返答に対し、フレンは視線を下方に落とした。ますますその表情が固くなる。
「どしたの? なんか、おっさん、まずいこと言った???」
「いえ、違うんです」
起き上がったレイヴンに、フレンはすっと頭を下げた。
「失礼は承知でお願いします。これを使って、僕と手合せしてくださいませんか?」
フレンが差し出したのは一振りの剣だった。ホワイトナイトソード――騎士の持つ剣。
「………これでか?」
フレンは頭を下げたままだ。
「……あー……、俺、剣を振ったら息切れしちゃうからね。まともな手合せにならないと思うよ?」
「体へのご負担が重くならない程度で……わずかな時間でもいいのです」
「やってあげればいいじゃない」
フレンは顔を上げた。
テントの近くで書物に目を落としていたはずのリタが、2人の方をじっと見つめている。
「別に命をかけて戦うワケじゃないんでしょ? それに、精霊のおかげで、おっさんの心臓、前よりは楽になってるみたいだし」
「ちょ…リタっち、か弱いおっさんが倒れたらどーするのよ」
「おっさんの心臓がどうにかなったら、あたしが治してあげるわよ。あたしを誰だと思ってんの?」
「天才魔道士少女、リタ・モルディオさんです……」
「分かってるじゃない」
リタはふんと鼻を鳴らして、また書物に目を落とした。レイヴンはその書物が何なのか知っていた。ガスファロストの地下、アレクセイの研究室に置いてあったものだ。
アレクセイが長年続けてきた魔導器の研究がつづられており、専門用語も多く高度な内容だ。知識の無い者には何が書いてあるのかすら分からないほど難解な文章を、少女は難なく読み進めている。
記述の中にはむろん、心臓魔導器に関する項目もあった。
それもレイヴンは知っていた。
「まー、フレンちゃんの頼みだしねえ。おっさんも気張ってみましょうか」
軽くのびをし、左肩をとんとんと叩く。
「すみません、レイヴンさん」
「おまえさんが気にすることじゃないわよ。ちゃんと手合せになるか、自信なくてね」
フレンから剣を受け取り、レイヴンは左手に握った。
直後、まとう空気が変わった。
剣が空気を裂き、ぶんと音をたてる。襲いくる刃を受け止めたと思った刹那、別の角度からまた、剣先が現れる。
力押しではなく、素早い動きから繰り出される計算された剣の振り。魔術までからめて、連携に持ち込んでくる。
(さすが……シュヴァーン隊長……)
フレンは荒い息をついた。
手合せになるかどうか自信がないなどと言ってはいたが、案の定、まったくの謙遜だったようだ。実際に戦ってみると、恐ろしいほどの手ごたえで、模擬戦と分かっているのに嫌が応にも本気になってくる。
(やはりお強い……)
バクティオン神殿でユーリと共に戦った時も思った。まさかこの方と戦うことになるとはと。戦慄が走るほどの強さは圧倒的で、みんなで協力したから追い詰められたものの、一対一で戦っていたら勝てたかどうか、今でも分からない。
(そうか…だから僕はシュヴァーン隊長と戦いたかったのか)
ぶつかり合う剣の向こうに、フレンのよく知る顔があった。感情を表に出すことなく、常に冷静沈着、威厳のある面持ち……。それは「レイヴン」の顔ではなかった。剣を握った直後、「レイヴン」の顔は彼から消えた。
フレンにはそう見えた。
「か弱いのではなかったのですか」
ウィンドカッターをすんでの所でかわし、魔神剣を繰り出す。地を這う斬撃を飛び越えるようにして、レイヴンはフレンとの距離をつめた。
「戦いのさなかに、おしゃべりする暇は無いはずだが」
舞うような動きとともに斬り裂いてくる刃をフレンはがっちりと受け止めた。
「ユーリほど饒舌ではありませんよ」
レイヴンは笑ったようだった。
「違い無い」
フレンの剣を受け流し、バックステップで距離をとる。力で勝負すれば押し負ける。それを分かった上での動きだった。
(本当に無駄がない)
フレンの中にますます闘争心が湧き立った。
もっと……もっとこの人と戦いたい!
「魔神連刃斬!!!」
斬撃を追うようにして一気にレイヴンとの距離を縮め、フレンは剣を振り上げた。
「フレンのヤツ、上手いことやりやがったな」
汗を拭きながら、ユーリはつぶやいた。隣でカロルが大の字になって倒れている。手合せといえど、体力は消耗するものだ。
「そうね、ユーリも本当はレイヴンと戦いたかったんですものね。騎士としての彼と、ね。なのに、フレンに先を越されてしまうなんて、私も残念だわ」
いつの間にか現れたジュディスに、ユーリは渋面になった。聞かれているとは思わなかったのだ。
「バッカじゃないの、アレ。手合せだって言ってたのに、術技使ってまでして戦って。めちゃくちゃ本気じゃない。休憩の意味あるわけ?」
げんなりした様子でリタは本を閉じた。
「あんたも戦闘バカだとは思ってたけど、さっすがあんたの友達だわ。フレンも相当な戦闘バカ。それに付き合ってるおっさんもおっさんだけど」
「レイヴン、大丈夫かなあ」
起き上がったカロルが心配そうに二人を眺めている。
「疲れたら言うでしょ?」
「私も心配です、リタ。知らず知らずのうちに無理とかしてしまうのではありません?」
エステルが言い終わるのとほぼ同時に、タイミングよくレイヴンが両手を上げた。
「ほら、心配ないでしょ?」
リタは再び本を開いた。まったく集中できやしないとぶつぶつと不平をもらしている。
「さすがにおっさん、参ったわー」
へろへろしているレイヴンとは対照的に、フレンは落ちる汗をぬぐうことなく一礼した。
「ありがとうございました。シュヴァーン隊長」
「だーかーらー、俺はシュヴァーンじゃないっての」
やれやれと言いながら、借りた剣を返そうとしたレイヴンの元に、ユーリは駆け寄った。
「おい、おっさん、まだ力余ってんだろ? 俺とやらないか」
ぎょっとしてレイヴンはユーリを見上げた。
「わ…悪い冗談だわ、それ。 鬼なの、青年ってば! おっさんの心臓、壊れちゃうわよ」
「そうだよ、ユーリ。レイヴンさんはお疲れみたいだし」
気遣うフレンを無視して、ユーリは剣を抜き、再びレイヴンの左手に握らせる。
「じゃ、これ食えよ。元気出るぜ」
右手の上に乗せられたレモングミを見つめ、レイヴンは、はあぁぁと大きなため息をついた。
「元気も何も……ったく、しょうがないあんちゃんだねぇ」
口の中にグミを放り込んでから、レイヴンはゆらりと剣を構えた。
「そうこなくっちゃな!」
傍目に見ても分かる、ユーリの高揚感。高ぶる気持ちを抑えられず、自然と不敵な笑みが浮かんでいる。
「いくぜ、おっさん!」
「本当に大丈夫かなあ、レイヴン。僕、すっごく心配になってきちゃった」
「私もです。続けて……しかも普段使わない剣を使って戦うのはあまり良くない気が……」
不安な表情でカロルもエステルも成り行きを見守っている。
「大丈夫でしょ、彼。ユーリやフレンと違って、ちゃんと自分を抑えて戦っているみたいだし」
「えっ、そうなの? ……ジュディスって、すごくちゃんと見てるんだね」
カロルは素直に感心した。ジュディスはどんな時でも心配りを忘れないが、それは観察眼が優れているからかもしれない……おぼろげにそう思った。
「あら、見たままの印象をそのまま言っているだけなのだけれど」
威張るわけでもなく、謙遜するわけでもなく、ジュディスは頬に手を当ててほほ笑む。
「やはりそう見えるんだね。僕もまだまだだな」
「あ、フレン! お疲れ! でも、ホントにそうなんだね?」
手合せを終えたフレンだが、どうしても気になるのだろう。ユーリとレイヴンの戦いに視線を置きつつ、仲間たちの所に戻ってきた。
「シュ……レイヴンさんは非常に落ち着いていたよ。だからこそ、どうにかしてあの人の気持ちを乱れさせたいと思ったんだが……僕の方が気持ちを抑えられなかったみたいだ」
「そういうとこ、あんたもユーリもホント、そっくりよね」
リタが書物から目を離すことなく、断言する。
「そっくりか……そうだね」
笑顔が広がる。それは肯定を意味しているようだった。
「ねぇ、フレン。剣を装備したレイヴンと、弓装備のレイヴンって、どっちが強いのかな?」
カロルが首をかしげながらたずねた。オルニオンでカロルはレイヴンと手合せしている。その時はもちろん、レイヴンの装備は普段通り弓と小太刀だった。
「難しい質問だね。何をして強いというのか、それはその場の状況や敵の種類によっても変わってくるからね」
「レイヴン……もしかして今なら、剣使って戦えるのかなあ?」
「それは絶対無理ね」
書物から顔を上げたリタが強い口調で断言する。
「え? やっぱりそうなんです? でもリタ、さっきは大丈夫だって言ってましたよね?」
目を丸くしたカロル同様、エステルもまた不思議そうにリタに問いかけた。
「あくまでも手合せだからよ。ジュディスも言ってたでしょ、抑えてるって。それに、手合せ程度なら心臓に負担がかかればすぐにやめられる。でも、実戦はそうはいかない。連戦になるかもしれないし、強敵を前にして倒すまで戦い続けることだってある。剣を握って至近距離で敵と戦い続けることが、どれだけ体の負担になるのか想像がつかないもの」
あたしでもね、とリタは戦う2人を見つめた。
ユーリの実践向きの術技を、レイヴンが流れるような剣さばきで時に受け流し、時に迎撃している。
「それよりは今のように後方から魔術や弓を使って、最後まで戦闘に参加できる状態の方が、レイヴンにとってもあたしたちにとっても最善だと思うわ」
「あら、珍しいわね。いつもケンカしてるのに、心配してあげるなんて」
ジュディスの言葉を、リタは過剰なまでに否定した。
「なななっっ、しっ、心配だなんて、何であたしがおっさんなんかの心配しなきゃなんないのよ!!! 途中でぶっ倒れでもしたら面倒でしょ! だからよっっ!!!」
「そうじゃ、やっぱり、そうなのじゃ!!!!」
リタの言葉に同意した……とは到底思えない、元気な声が上がった。
「ど、どうしたのパティ、突然…」
今まで大好きなユーリを凝視していたためか大人しかったパティだが、突然何か思い立ったようにみんなに向き直った。
「おっさんとユーリの動きは違うのじゃ」
「いや、違うって見たままじゃない」
あきれ顔のリタに対して、パティは一歩も譲らなかった。
「でも、おっさんとフレンの動きはおんなじだったのじゃ」
「何それ。意味わかんないんだけど。そもそも技とか全然違うじゃない」
「パティ、君はよく見ているね」
パティに話しかけるように……それでいて、怪訝な様子のリタやエステルにも分かり易いよう、フレンは穏やかな口調で説明した。
「僕とレイヴンさんの動きは似てて当然なんだよ。騎士団に入ればまず、徹底的に騎士の剣を覚えることになるからね。剣をどう構えるか、どう扱うか、剣技や立ち居振る舞いも含めて基礎や伝統があるんだ」
「あ、そか。それでこの間ユーリともめてたんだね。伝統ある騎士団の技に蹴りやパンチを加えてるって」
同じ技でもユーリとフレンとでは微妙に違う……それに気づいたのはカロルだった。
逆にいえば、使う技が違っていても、基本的な剣の扱い方が同じならば、動きが似てくるのは当然だということだ。
「シュヴァーン隊長が「レイヴン」として活動する時、もちろん、心臓のこともあっただろうが、剣を使わないというのは正しい選択だったと思うよ。騎士団の者なら、剣の扱い方を見れば騎士かどうかなんてすぐに分かってしまうからね。ギルド側にも元騎士団の者もいるだろうし、素性を隠すという意味では、剣を武器として用いることは危険を伴ったはずだ」
「そうかあ。レイヴンって何にも考えてないように見えるけど、そうでもないんだね」
「実際、何にも考えてないんでしょ」
感心しきりのカロルをよそに、リタはあくまでも冷淡だった。
「彼、いつもふざけてばかりだけど、それも計算のうちなのかも、ね? 騎士としての品格を隠すための」
「前にもジュディス言ってたよね。でもそれって、全部嘘ってことなの? 僕、レイヴン好きだよ?」
「嘘…ではないと思います、カロル」
エステルが両手を握りしめて力強く言った。
「レイヴンは、すごく活き活きしている気がしますから!」
「いろんな意味ででしょ? エロオヤジすぎるのなんて最悪じゃない」
むしろ滅したい……そんなリタの手厳しい意見に、ジュディスはふふっと笑った。
「そうね。確かに活き活きとしているわね。だって彼、レイヴンとして生きることを選んだのだもの、ね」
自然とみんなの視線が今だ剣を振るっている2人の男に移った。
元騎士と、元騎士団隊長首席。ともに騎士団を去り、ギルドの人間として生きることを選んだ。
フレンの眼差しがすっと遠くなる。
「やはりあの方は騎士の中の騎士だ……今でも……」
かすかなつぶやきは、リタの耳には届いた。
部下たちの態度でも分かる。限りない尊敬を受けていた「隊長首席」。フレンの目にもまた、「レイヴン」は違う姿で映っているに違いない。いやむしろ、フレンや部下たちが見ている姿こそが、元々の彼の姿……本来の彼なのだ。
「レイヴン」という存在は、10年前にアレクセイの命令によって造られた架空の存在なのだから。
そう思ってから、リタはぶんぶんと首を振った。
「おっさんは、どーせおっさんなのよ」
締めくくるような一言と同時に、レイヴンがばたんと倒れた。
一瞬、全員に緊張が走る。
「もうダメ〜。おっさん限界よー」
「なんだよ、いいところだったじゃねぇか」
ユーリはまだまだやる気満々のようだ。全身から闘志がみなぎっている。
「若いってすごいわね……ホンっと羨ましいわ」
レイヴンが愚痴のような一言をもらしている。
「だ、大丈夫みたいだね」
カロルは胸をなでおろした。ほっとしたのも束の間、フレンが慌てて2人に駆け寄る。
「ユーリ、君は……手合せなんだから、そこまで本気にならなくてもいいだろう?」
非難され、ユーリは憮然と言い放った。
「俺、おまえにはそれを言われたくないけどな」
「僕は君ほど夢中で戦っては……」
「いや、マジだったろ? さっき」
「確かに本気な部分はあったが……君ほど技ばかり使ってはいなかったよ!」
「はあ? 俺がおまえより技使ってたっていうのかよ」
口論を始める2人に、リタが閉口する。
「仲良すぎるってのも、面倒くさいわね」
「ねー……おっさんは? みんなおっさんのこと忘れてなぁい?」
どうしていつもこうなるのとばかりに、レイヴンが悲しげな声で訴えた。
「ほれ、おっさん、おでんでも食って、元気出すのじゃ」
トコトコと歩いてきたパティが、どこからともなくおでんを差し出す。
「パティちゃんは優しわねー。リタっちとは大違い……」
「何でそこにあたしの名前が出てくるのよ!!!」
リタの音速ツッコミが入った。
「リタ姐、すぐ怒るから面白がられているのじゃ」
「……パティちゃん、意外と鋭いこと言うわね……」
「うるさぁぁああい!」
リタは顔を真っ赤にして怒鳴った。
「おっさん、ここは逃げるのじゃ」
「らじゃーよ」
「こらぁー待ちなさぁぁぁーーい!!!!」
どこにそんな元気があったのか、一目散に逃げるレイヴンをリタが鬼の形相で追いかけている。
ユーリとフレンはというと、口では決着がつかなかったのか、互いに剣を構え戦い始めていた。手合せなのか本気なのかよく分からないほど剣戟は激しく、全力を尽くしているように見える。
「みんな、仲良しなのじゃ!」
嬉しそうに、パティが右の拳を空に向かって付き上げた。
「仲良しって……確実に一件はパティが火に油を注いだ結果だよね?」
カロルが魂の抜けたような目をしたままぼそりと言う。
遠くからレイヴンのギャーという悲鳴が聞こえてくる。想像にしかすぎないが、あんまり穏やかな状態ではないようだ。
「あら、ケンカするほど仲がいいと言うし、いいんじゃないかしら」
「そうですね、ジュディス。フレンもユーリも、なんだか楽しそうです、とても」
リタとレイヴンも楽しかったらいいんだけど……とカロルは思ったが、口にはしなかった。
「みんなきっとお腹がすくと思うから、料理でも作って待ってようかな」
「えらいわね、カロル。さすがブレイブ・ヴェスペリアの首領(ボス)だわ。みんなのことが大切なのね」
「えっ、そうかな」
後頭に手を当てて照れるカロルに、エステルとパティは顔を見合わせ、くすっと笑った。
「やっぱりみんな……」
「仲良しなのじゃ!!!」
「ワンッッ!!!!」
--------------------------------------
※参考スキット…「隊長の品格」「ユーリとフレンの術技」「青春の証」「最終戦への意気込み 男性編」
+++読まなくてもいい話+++
フレンにとって、レイヴンはシュヴァーン隊長みたいですね。
戦闘後のセリフでも、「やりましたねシュヴァーン隊長!」とかいうのがあって萌えた!
そのあと、レイヴンに否定されて「レイヴン隊長」って言い直し?してて、ルブランと同じかーーーー!!!!! とまた萌えました。
レイヴンが剣を使わないのはまあ仕方ないんですけど、もし使ったなら、それは騎士としての基礎がガッッチリ出来てる剣なのかなあと勝手に想像してます。そして剣を握ったら、隊長に戻る……気がしてこんな小説になりました。
フレンとレイヴンの心の交流?みたいなものを描きたかったのに、結局レイヴンとリタのケンカ落ちに??
スミマセン………。
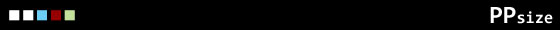
2009.10.25.
|