「ほれ、みんな、出来たわよ〜」
レイヴンの呼びかけに、カロルは素振りをやめ、テントの中からリタとエステルが這い出てきた。
「うわー、いい匂い♪」
レイヴンが運んできた料理にカロルが目を輝かせる。ユーリも剣を磨く手を止めた。
「今日はサラダと牛丼か……中々バランス取れてるじゃねぇか」
「バランスぅー? 何となく料理の雰囲気が違う気がするけど。あたしならサラダにはハンバーグね!」
「あー、でもリタっちってば、つなぎも調味料も入れずに、ただのひき肉のカタマリを焼いちゃったじゃない……」
「はーっっっ!!!!」
テーブル代わりの道具箱に料理を置いた瞬間、リタのローズウィップがうなりを上げてレイヴンの背中を襲った。
「ぐはぁぁぁっっ」
背中を押さえて痛がるレイヴンの隣で、おそるおそるカロルは言ってみた。
「……リタ……ムチは……ムチ装備の時はやめてあげようよ……」
リタはつーんとそっぽを向く。
「おっさん、体鍛えてるみたいだから大丈夫よ」
「だ……大丈夫じゃ……ないです……」
「まあ、組み合わせはともかく、だ。おっさん、意外と料理、上手いよな」
箸を器用に使いながら、ユーリが牛丼を頬張っている。
「ダメですよ、ユーリ。ちゃんと『いただきます』って言ってからじゃないと」
「イタダキマスー」
棒読みするユーリに、エステルは「もう、ユーリったら!」と頬をふくらませる。
「確かに美味しいよね、レイヴンの料理」
カロルもまた夢中で頬張っていた。
「カロルの言うとおりです。レイヴンって、料理が上手ですよね。私も見習わないと……」
手をちゃんと合わせてから、エステルも料理に舌鼓を打つ。
「そうね。手際もいいし、深みのある繊細な味ね」
「えっっ!? ホント、ジュディスちゃん!!! おっさんに惚れちゃった?」
「うふ。私の方がもっと美味しく作れるけれど」
艶然とほほ笑まれ、レイヴンはがっくりと肩を落とした。
「そうですねー」
みんなのやり取りを横目で見ながら、リタはうーと唸った。
一口、サラダを口にすればすぐわかる。新鮮な生野菜のもつ本来のおいしさを活かし引き立たせる絶妙な配合のドレッシング。あくまでシンプルに、しかしながら、決してあきさせない。
一方牛丼は、辛すぎず、甘すぎず、ダシも良く効いたツユだく仕上げ。牛肉はどこまでも柔らかく、対して、玉ねぎには丁度いい歯ごたえを残し、えもいわれぬアクセントになっている。一度食べたら最後、止まらなくなる美味しさだ。
「そっ…そりゃ確かにおっさんの料理はまあまあの味だけど……でも、おっさんの発想って変だわ! この前だって、スコッチエッグからヒントを得たとかで、お好み焼作ってたし!」
「あのお好み焼き、とても美味しかったです」
「リタもエステルみたいに、素直に美味しいって言えばいいのに……」
うつろな眼差しを向けたカロルに、リタの音速チョップが炸裂する。
「何よ、間違ったこと言ってないでしょ! じゃ、カロルとおっさんに聞くけど、牛丼からどんな料理、思い付く?」
額を押さえていたはずのカロルは、痛みなど吹っ飛んだのか、即答した。
「ボク、オムライスー!!! 同じご飯ものなんだけど、卵をふわふわに仕上げたら、きっと美味しいと思うんだ!」
「わあ! 美味しそうですね、カロル。ぜひ食べてみたいです!」
興味津々のエステルにカロルは得意そうに胸をそらした。
「まかせてよ、エステル! 次の料理当番の時に腕によりをかけて作るからね」
「……ライスしか、つながりが無い気がするけど……」
リタは額に手を当てた。カロルに聞いたのが間違いだったのか……。
「ねー、聞いて聞いてー♪ おっさんがぁー、思いついたのはぁー」
レイヴンは立ちあがり、箸で天を刺した。
「おっさん……うざっ」
「何よー、リタっち! ちゃんと聞いてよー」
「何、思い付いたんだ?」
完食したユーリはごろんと横になり、さして興味がある風でもなく尋ねた。
「もう、ユーリ。お行儀が悪いです。食べた後、すぐ横になったらダメなんですよ」
「何で、ダメなんだ?」
真顔で尋ねられ、エステルは小首をかしげだ。
「ええと……何ででしょう?」
ユーリは少し吹いた。
「あの二人、旅の間、ずっとあの調子ね。微笑ましいわ」
マナーにのっとった美しい所作で食事をとっているのはジュディスだ。
「エステルもエステルだけど、ユーリの行儀の悪さは折り紙つきよね。ホントに元騎士なわけー? 今だに信じられないわ」
リタにとって、もう一人の「信じられない人」であるはずのレイヴンは、しゃがみこんで地面に円をぐるぐると書いている。
「……あの、おっさんは? ねー、おっさんの話、みんな聞こうよー……?」
「そ、そうだよ、そもそもリタが聞いたんでしょ?」
カロルは、いじけたレイヴンを支えるようにして立たせた。ダメなレイヴンを、これ以上見ていられなくなったのだ。
「カロル少年は優しいわー。天才魔道少女とは大違……あだっっ」
身長差をもろともせず、リタのチョップがレイヴンの鼻を直撃する。
「で、おっさんは何、思い付いたのよ」
「おっ……おっひゃんはね……」
鼻を押さえながらも、レイヴンは少しでも尊大に見せようと胸を張った。
「豚の角煮! どう? 美味しそうでしょ!?」
辺りは静まり返った。
「アレ?」
レイヴンはあまりの反応の無さにきょとんとする。
「ある意味すげぇよな、おっさん。ビーフからポークだからな」
一瞬の間を置いてユーリがぼそりと言った。
「何というか、予想を超えてますよね!」
エステルが励ますように後を続ける。
「ご飯からおかず……かあ」
カロルに至っては、何と返していいのか、全く分からなくなってしまっている。
「ほーら、見なさいよ、おっさんの料理に対する感覚って、結局こんなもんなのよ」
腕組みしたまま、リタは得意満面だ。
「あら、煮るという点や、味付けに関していえば、そう遠すぎることもないと思うのだけれど?」
ジュディスが至極もっともな意見を述べると、レイヴンは飛びあがった。
「もー、ジュディスちゃんなら、分かってくれると思ってたわー」
「似た系統だとも言ってはいないけれど、ね」
「ええー……?」
ジュディスの一言にレイヴンはうなだれる。
あまりの浮き沈みの激しさに、リタは再び「うざっ」ともらした。
「おっさんの感覚って、やっぱ、有り得ないのよ」
「そーゆーリタっちはどーなのよ? おいしい料理作れないじゃな……げふっっ」
「……レイヴン、リタに殴られるって分かってるのに、勇気あるよね……」
疲れたようにカロルがつぶやき、エステルはおろおろした。リタの所業はいつも、とても手加減しているように見えないからだ。
「そうだな。とりあえず、ここは公平に、だ。サラダからどんな料理を開発できるか言ってみたらどうだ?」
「そうですね、今食べたばかりですし、想像しやすいかも」
ユーリの妥協案にエステルも賛同した。
「とりあえず、リタならどんな料理を考えます?」
エステルに問われ、リタはあわあわした。あまり料理が得意ではないし、そもそもサラダなんて生野菜にドレッシングをかけて食べるだけではないか?
「そ、そうね。あっ、あたしなら………野菜を……焼くわね!」
「ちょ、リタっち、焼くってまたストレートな……」
あきれ顔のレイヴンとは対照的に、エステルは両手を胸の前で組んで目をキラキラさせた。
「さっすが、リタです! それって野菜炒めってことですよね!お野菜を油で炒めて胡椒と塩を振って……美味しそうです!」
ええっ?という面持ちでレイヴンがエステルを振り返った。
「じゃー、次はレイヴンですね」
にっこりとほほ笑まれ、レイヴンは何も言えなくなった。
「おっさん、早く言えよ」
ユーリはすでに飽きているのか、横たわったまま腕まくらをし、今にも寝入りそうな勢いだ。
「俺様なら、そうね」
レイヴンは少しだけ考えた。
「俺様なら……お刺身ね!」
再び周囲に満ちたのは、何ともいえない静けさだった。
「ええと……何なの……それ?」
想像できなかったカロルは、とりあえずたずねてみた。
「お刺身はねー、ほら、マグロとか、サバとか、イカとかあるじゃない? そーゆーのを生のまま切り身にして、お醤油をつけて食べるのよ」
「それって料理なわけ!?」
リタがすかさずつっこむ。
「あ、ちゃんとした料理ですよ。しかも新鮮なお魚を使わないと美味しくないので、むしろ高級です」
フォローを入れたエステルであったが、リタはふんと鼻を鳴らした。
「全っっっっ然、サラダとつながりないじゃない。野菜から魚って、おっさん、どーゆー思考回路してんのよ」
「カケラもかぶってないよな」
ユーリも鋭く指摘した。
「だって、ここは意表を突いた方が楽しいじゃない!!! 発想の転換よ、て・ん・か・ん。頭の固いリタっちには想像もつかなかったでしょ!?」
「はぁぁああぁぁ???」
レイヴンの主張は、リタには全く認めてもらえなかった。それどころか、リタの怒りの導火線に点火しただけだった。
「よくもそんなセリフが吐けるわね、おっさん! 真面目に考えてなかったってことじゃない!!!!」
リタの周囲に魔方陣が浮かび上がる。
「ちょ……ちょっとリタっち?」
「………火焔の帝王、地の底より舞い戻れ……」
青ざめたレイヴンはそのままずりずりと後ずさり、直後、全速力で逃亡を計った。
が、到底間に合うはずもなかった。
「イラプションーーーー!!!!」
「ギャーっっっ!!!!」
突如吹き出した溶岩が、レイヴンを直撃する。業火に包まれ、すぐに姿が見えなくなった。
「最初はストーンブラストくらいだったのに、リタ、だんだんエスカレートしてるよね」
「何? なんか文句ある?」
「……ないです……」
半眼でにらみつけられ、カロルはひきつった笑いを浮かべたままお皿を片づけ始めた。
炎が収束し、黒こげになったレイヴンが現れると、エステルがすぐさま駆け寄った。必死に治癒術をかけている。
「おっさん、生きてるかあー?」
ユーリが声をかけると、かすれた声で「生きてる…かも?」と返答があった。
「ま、大丈夫みたいだな」
やれやれとユーリは身を起こした。
「あら、寝ててもいいのよ?」
他の人の皿まで丁寧に片づけながら、ジュディスは労りとも無関心とも取れる口調でいった。
「あんだけ大騒ぎされて、寝られるわけねぇだろ?」
ユーリが盛大なため息を吐いた直後、聞き捨てならないとばかりにリタが割り込んできた。
「大騒ぎって何よ」
「あんまりおっさんをいじめるなってことだよ」
一瞬ぐっと詰まったリタだったが、ふんっとそっぽを向いた。
「あんた、意外にもレイヴンをかばうのね」
「あら」
ユーリの代わりに応えたのはジュディスだった。
「エステルが無理しないか心配なのよね?」
謎めいた笑みを口元に浮かべたまま、さらに続ける。
「リタもそう。本当は、エステルがああしてくれるって分かっているから、レイヴンと思いっきりケンカ出来るのよね? 力を使うことで命を削ることのなくなった今だから」
ユーリもリタも無言になった。
「私、何かおかしいこと言ったかしら?」
「あー……あたし、明星弐号のメンテナンスしないとー」
「あー、俺も、剣磨きかけだったんだよな」
ユーリとリタはまるで示し合わせたかのように、それぞれ男子テント、女子テントに引っ込んでいった。
「うふ、おかしな人たち」
ジュディスから手渡された食器を洗いながら、カロルはラピードにそっとささやいた。
「ボク、分かっちゃったかも。もしかして最強なのはジュディスなんじゃないかなあ」
「ワンッ」
ラピードの吠え声が、タルカロンの塔にこだました。
--------------------------------------
+++読まなくてもいい話+++
移植版では、たまにパティに料理を作ってもらったりしてますけど、今のところ開発出来てません…。
フレンは4回連続失敗をした後、あきらめました……。
しかし、おっさんの開発する料理ってどれもこれもハテナです。もちろん、他のキャラでもたまにハテナがありますけど、レイヴンはホント、発想が豊かすぎ♪
とりあえず、タルカロンでも、レイヴンはだだこねたり、オモシロスキット?らしきものも発生してたので、みんな休息時間はこんな楽しげでもいいかもとか思って捏造してみました。
あ、ちなみに、リタの開発した“野菜炒め”からレイヴンが開発したのは“タンメン”です。タンメン……。
+++読まなくてもいい話その2+++
ヴェスペリアの世界の料理ってどうなってるのかイマイチ謎です。和食ってあるのかな?いや、料理開発できるんだからあるだろうけど、どちからというと洋食のイメージが強いです。なんとなく。なので、基本、和食はあんまりなじみのない料理という扱いで、上のような小説になりました。スミマセン…。
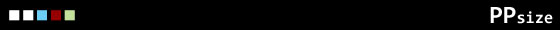
2009.10.13.
|