がっくりと肩を落とし、アデコールとボッコスはとぼとぼと城へ戻ってきた。
今頃、上官であるルブラン小隊長は、シュヴァーン隊長に事の顛末を報告していることだろう。その内容は、全くかんばしくないもので、2人とも考えるだけで気分が重かった。
「また、ユーリ・ローウェルにしてやられたのだ……」
「投石などという野蛮な手段は、禁止にすべきなのであ〜る!」
脱獄したユーリをくまなく探し、どうやら城の外へ出たらしいと気づき追ってはみたが、すんでの所で逃げられた。
正確にいえば、一度は追いついたのだが、ユーリ・ローウェルの適格な投石がアデコールとボッコスを直撃し、二人そろってのびてしまったのだった。ルブラン小隊長が一人で追ったが、市民の妨害に会い、取り逃がした。
ローウェルだけならば、アデコールもボッコスもこんなに暗い気分にはならないだろう。
こともあろうに、ユーリ・ローウェルはエステリーゼ姫様を連れて逃亡したのである。
「まさか姫様を外に連れ出すとは…なのだ」
「恐れをしらぬ、不届き千万なヤツなのであ〜る」
2人そろって、大きなため息をついた。
これで、ローウェルは脱獄罪だけでは済まなくなった。皇族の誘拐というとてつもない大罪を犯したことになる。
2人が見た限りでは、姫様自ら、ローウェルについていったようにも見受けられたが。
「おやぁ〜、下民一人捕まえられなかった無能な2人組じゃないか」
シュヴァーン隊の詰所を目前にしながら、2人は足を止めざるを得なかった。
「これは、キュモ〜ル隊長」
アデコールが姿勢を正した。慌ててボッコスも「きょうつけ」の姿勢を取る。
「聞いたよ? また、ユーリ・ローウェルを取り逃がしたんだって? しょせんは、生まれの卑しい者たちが集まったヘナチョコ隊……おっとこれは失礼。君たちのシュヴァーン隊長も同じ平民出だったよね」
2人は押し黙った。ユーリを捕えることが出来なかったのは、まぎれもない事実だ。だが、シュヴァーンにまで話が及ぶと、その心中は穏やかではなくなった。
(我々が到らないばかりに、隊長が侮辱されているのだ……)
(シュヴァ〜ン隊長はゆくゆくは騎士団長になるお方なのであ〜る。……今だって、キュモ〜ル隊長より偉いのであ〜る)
唇をかみしめ、それでも2人は沈黙を保った。騎士団の隊長と、下級騎士では階級に差がありすぎる。反論など許されるはずがなかった。
キュモールは口元に嫌な笑いを張り付け、胸をややそらし、尊大な様子でなおも続けた。
「君たちのようなマヌケな騎士を、除隊させずに使うだなんて、シュヴァーンにはあきれるね。いや、君たちのような騎士が居るから隊長がマシに見えるのかな? 自分の無能を隠すには、ちょうどいいのかもね」
シュヴァーン隊の詰所が近いだけに、その場にはアデコールとボッコス以外のシュヴァーン隊の騎士も居た。
キュモールの平民出の騎士に対する侮蔑や偏見は、今に始まったことではない。だからこそ、2人はさらに顔をこわばらせた。
同じシュヴァーン隊の騎士からも「できそこない小隊」だと言われることがある。非難の理由は分かっていた。部下の失敗が隊長の評価に直結するからだ。
シュヴァーンの名を高めたい……その気持ちは隊の者の多くが共有するものだった。
腕組みをし、キュモールは皮肉を隠さなかった。
「本当に君たちみたいな何をやってもダメな人間は、クズ以外の何者でもないよね。僕の隊ではとても扱えない……」
「私の部下にどのような用件がおありか?」
キュモールはギョッとして声のした方を振り返った。
階段から降りてくるのは黄金色の鎧をまとった黒髪の人物――まぎれもないシュヴァーン隊長、その人だった。
背後には数名の小隊長が付き従っている。その中にはアデコールとボッコスの上司であるルブラン小隊長の姿もあった。
キュモールはふんっと鼻を鳴らした。
「用……そうだね、館に不法侵入していた下民一人捕えることができず、代わりに僕の部隊が逮捕してあげたからね、その礼を受けていたのさ」
「あ……その件につきましては……」
ボッコスが声を上げ、すぐに視線を落とした。キュモールにきつく睨まれたからだ。
「まったく君の部下は有能だね? ユーリ・ローウェルみたいな小物を捕えることができないばかりか、反対に打ち倒されているんだから。2人がかりで対処してこの有様とはねぇ」
騒ぎを聞きつけて僕が駆けつけなかったら、どうなっていたかとキュモールは哄笑した。
拳をにぎりしめ、ボッコスは悔しさを押し殺した。
貴族街のとある屋敷から現れたユーリ・ローウェル。明らかに現行犯逮捕できる状態だった。だが、逆にやっつけられ、直後に現れたキュモール隊にその場の主導権を握られてしまった。
その時に、「シュヴァーン隊長には内密に」とボッコスはキュモールに願い出た。シュヴァーンにより与えられたユーリ・ローウェル捕縛の機会を、無様にも逃してしまったことへの恥と無念がそうさせたのだ。だが結局、多くの騎士の前で、その恥は明るみになってしまった。
「シュヴァーン隊には有名な“できそこない小隊”が居るそうだけど、隊長である君の管理が行き届いてないんじゃないかい?」
「お言葉ですが、キュモール隊長。シュヴァーン隊長に対して、いささか礼儀に反した言葉遣いをされていらっしゃるようですが?」
声を発したのはルブランだった。その表情はあくまでも厳しい。だがキュモールは意に介さなかった。
「その“できそこない小隊長”が何を言うのさ。貴族であり騎士団の隊長である僕に対する口のきき方を知らないみたいだね」
騎士団の階級でいえば、同じ隊長でも首席であるシュヴァーンの方が上である。実質的には騎士団長に次ぐ地位ともいえる。だが、キュモールは貴族という身分をかさに着て、常にこのような態度を取っていた。
「僕のことをどうのこうの言う前に、シュヴァーン、君がイチから教えた方がいいんじゃないのかい?」
ルブランは何か言いたげな様子であったが、ぐっとこらえ、「失礼しました」と一礼した。
キュモールは愉快でたまらないようだった。
「聞いたよ? 今もまた、脱獄したローウェルを取り逃がしたそうじゃないか。部下の犯した失態は隊長である君の責任じゃないのかい? 僕なら恥ずかしくて城内を歩くことすら出来ないね」
「貴公の言うことももっともだ」
シュヴァーンの言葉に、シュヴァーン隊の騎士たちは一様に表情を曇らせた。キュモールが剣もろくに扱えず、指揮官としての才にも乏しいことは、周知の事実だった。その彼から受けた侮辱を、シュヴァーン隊長が認めざるを得ないでいる……その起因を引き起こしたアデコールとボッコスは身を小さくした。この場から消え去ってしまいたかった。
「なら君が全ての責任をとって……」
得意満面のキュモールに、シュヴァーンは全てを言わせなかった。
「なるほど、部下の失態の責任を隊長が負うというのは、帝国の騎士を束ねる者の一人として当然のことだ。聞けば、ローウェル脱獄の際、地下牢当直の騎士は貴公の隊の者だったとか」
寝耳に水だった。
「な……?」
呆然としたまま、キュモールはシュヴァーンを見つめた。
「脱獄を防げなかった騎士に対し叱責も処分もなく、貴公自ら責を負うとは、私も見習わなければならぬようだな」
淡々とした口調である。しかし、見習うと言いながら、実際には痛烈な皮肉であった。
そのことが分からないほど、キュモールは愚かではない。
ユーリが脱獄して城内が大騒ぎになっているちょうどその時、キュモールは貴族街を巡回中であり、しかも、自宅で勝手に休憩まで取っていた。城に戻り、城内に居た部下から大体のいきさつを聞いたが、部下たちはキュモールを喜ばせるためシュヴァーン隊の失敗ばかりを彼の耳に入れたのだった。
ぎりぎりと歯を噛みしめる。
牢番に当たっていたのは誰だ?すぐにそいつも、そいつの家族もみんなヘリオードにとばして、労働者キャンプに送りこんでやる………
その時、別の人物の声がした。
「ほう。キュモールよ、そなたも隊の長としての心構えが出来るようになったか」
「ド……ドレイク顧問官……」
階段からもう一人、立派な鎧に身を包んだ老人が降りてきた。
ドレイク・ドロップワート、先代皇帝の剣の指南役であり、騎士の鏡と謳われる人物だ。騎士団にあってその名を知らぬものはない「尽忠報国の騎士」である。一線を退いた現在は、騎士団の顧問官として、騎士団長や各隊長に助言を与える立場にあった。
「ぼ……僕は別に……」
「部下の責任を取るのであろう?」
(シュヴァーンめ……)
最初から、ドレイクが居ることを承知の上で、あのような発言をしたのか。
「せ…責任はシュヴァーンが……そうだよ、事の発端はこいつらが……」
アデコールとボッコスは大量の汗を額に浮かべたまま、直立不動の姿勢を崩さなかった。ドレイクは彼らをちらりと見やる。
「ローウェル逮捕の際には、シュヴァーン隊の2名が犯人の居場所を迅速につきとめ、不法侵入の現場をおさえた後、キュモール隊が応援に入ったと聞いているが? 違っていたのか?」
ドレイクの言葉は誤りではない。誤りではないのだが、キュモールは苛立ちを隠さず、シュヴァーンに視線を移した。
ものは言いようとはよく言ったものだ!
だがそこにあったのは、何の感情も映さない青みを帯びた瞳だけだった。
「私はすでに、ローウェルの脱獄及び姫様の拉致について、団長閣下に報告に上がっている」
シュヴァーンの言葉にキュモールは飛び上りかけた。
「ひ…姫様が拉致!?」
「また、城内に侵入した暗殺集団については、数名を泳がせ、現在、我が隊の一部に後を追わせている」
「暗殺集団……城の中にかい? 嘘だろう?」
ドレイクが眉根を寄せた。
「侵入経路を辿った結果、そなたの隊の騎士のうち、数名が絶命していたという。知らなかったのか?」
距離を置いて様子を伺っていたシュヴァーン隊の騎士たちに、さざ波のようなざわめきが起こる。
はっきりと言葉が聞こえたわけではない。それでも、キュモールは自分が無能だと言われているような気がした。激しい憎しみが湧きあがった。
平民出の……卑しい身分のおまえたちが、貴族である僕を侮辱するだと? ……許さない…許さないぞ!
「このたびの件については」とシュヴァーンが抑揚のない声を発した。
「騎士団長閣下が全責任を負い、死亡した騎士については昇格、及び報償金を与えるそうだ。貴公も内容を取りまとめ、報告に上がるように」
「ぼ…僕に命令する気かい?」
「騎士団長閣下からのご命令だ」
「そ…そんなことは分かっているよ!! アレクセイ団長閣下様が全ての責任を取ってくれるんだろ? だったら僕も…僕の隊も関係ないってことじゃないか」
ドレイクが憂いを帯びた目でキュモールを見つめた。
「本当にそなたはそう思っているのか? シュヴァーンが何を言ったか聞いていたであろう?」
「報告には上がるよ、ちゃんとね。僕を誰だと思ってるんだ」
吐き捨てるように言って、キュモールは足早にその場を去った。
小言の多い顧問官も、平民出の成り上がり隊長の顔も、もう見たくはなかった。
(シュヴァーンを見習えとでも言いたいのか!)
悔しさと苛立ちがない交ぜとなり、キュモールは歯をきつく噛みしめた。
(人魔戦争の英傑? 運良く生き残っただけじゃないか。それをアレクセイが……)
大体、何をどう報告するというのだ。そんなもの全部文官に任せておけばいい。いちいち目を通すのも面倒だ。
床を踏み鳴らしながら歩くキュモールの後を、あわてて取り巻きの騎士たちが追いかける。
人気のない回廊の端まで来たところで、キュモールは付き従ってきた騎士たちを追い払った。
みんなハエだと思った。自分の周りを飛び回るうるさいハエだ。
壁を蹴りつけ、剣を振りまわしたい衝動にかられた。だが、貴族としてのプライドが思いとどまらせた。
みんなクズだ。僕のような高貴な者に対する礼儀を知らないクズばかりだ……。
握りしめた拳が震えた。
「焦るでない」
落ち着いた声音が響いた。回廊の端に、いつのまにか老人の姿があった。
ドレイク顧問官だった。
「焦るでない、アレクサンダーよ」
これまで数々の助言や苦言をキュモールに与えてきた顧問官は、静かな眼差しのまま距離を置いてたたずんでいた。
「知らぬことが恥だと分かるそなたなら、まだ間に合う。今いちど初心に立ち返り、一人の騎士として学ぶ気はないか」
「現役でもないのに、いいかげんに小うるさいですね。僕はもう子供じゃないんだ」
キュモールは努めて平静を装った。
「僕はもう騎士団の隊長なんですよ。たくさんの小隊を持ち、動かしてるんだ。そもそも隊長首席の座だって、成り上がりが任命されなければ……」
「……権力の鉈(なた)を振り上げることで、ある程度の者はそなたの命に従うだろう。だが真に他者の尊敬を集めたいのであれば、そなたが動かしたいと思う者たちの思いを組み取ることもまた、必要だ」
「騎士は“心”? その話は聞き飽きましたね」
せせら笑うキュモールに対し、ドレイクは微動だにしなかった。
「剣技が得意でなければ、人の倍、剣を振ればよい。組織を掌握したいならば、現場との関わりを密接にし、己の目で見つめ己の耳で聞くとよい。知略に長けたいのであれば、各地を巡り書物を開き、ひたすらに学べばよい。努力の積み重ねは決して無駄にはならぬ」
「しょせんは、方便ではないですか。それで実際に身に付くわけではないでしょう?」
そんなものよりも、何よりも、“血筋”が大切ではないか。後から決して得ることのできない最も尊いものではないか。
「アレクサンダーよ、何もしなければ結局、何も身に付かぬ」
キュモールの白い顔にさっと朱が走った。
「今からでも遅くはない。暴挙に走らず、己を見つめなおし、学ぶ準備が出来たなら、私の元に来るとよい」
背を向けた老人が回廊から姿を消すまで、キュモールはギリと唇を噛みしめ、剣の柄に手をかけたまま見送った。
(老いぼれが偉そうに……)
柄にかけた手を、力なく下ろす。
最初から剣を抜くつもりはなかった。むしろ抜くことなど出来るはずもなかった。。
仮に抜いたとしてどうするのか。年老いてはいるが、先帝の剣の指南役を務めていたドレイクに勝てるはずがない。それどころか勝負にすらならないだろう。
痛いほど分かっていた。それほど剣の腕には自信が無かった。
真実を知らせない部下たち、騎士団長の不可解な命令、人望を集める成り上がりの隊長……全てが気に食わなかった。
呪文のように繰り返し、繰り返し、自分自身に言い聞かせた。
僕は貴族なんだよ?
騎士団長よりも古くて由緒正しい家柄なんだ。
貴族街にキュモール家よりも素晴しい館があるかい?
騎士団の中でも、僕が一番素晴らしい血筋の生まれなんだ。
僕は本来なら評議会の一員にだってなれたんだ。
貴族の御婦人方だってみんな僕に夢中さ。
みんなこぞってお金を差し出して、僕の機嫌を取ろうとする。
それほど僕の存在は大きい。
そうだ、僕は一目おかれているんだ。
シュヴァーンだって、アレクセイだって、みんな僕を怒らせたくないはずだ……
だって僕は……僕は……僕は………。
キュモールは床を見つめた。激しく歪み、今にも泣きだしそうな顔が、磨かれた石面にうっすらと映っている。
僕は……僕には……。
映し出された醜い顔を、自分の足で踏みつけた。
僕には………何もない。
…………何も……ないんだ…………。
--------------------------------------
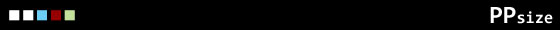
2009.08.11.
|