遠目に見ても、明らかにその街は姿を変えていた。
なぜなら男は一度この街にわずかながら立ち寄り、失われた結界と傷ついた人々を目にしたからだ。その後、学術都市アスピオの付近まで足を伸ばし、用を済ませて戻ってきてみれば――町は全く違う姿となっていた。
青空の元、なお、光り輝く巨大な結界。季節はずれとしかいえないほど、咲き誇っているハルルの樹。
「こりゃ……たまげたねぇ」
男は誰ともなくつぶやいた。つい昨日、彼が見た姿とは正反対だ。彼が見たハルルの樹は今にも枯れそうなほど弱々しかった。葉に生気はなく、しおれ、くすんでいた。
それが、こんな短時間でここまで回復するとは奇跡としかいいようがない。
何かがあったのだ。
「あいつら……何かしたのかね?」
昨日立ち寄った時、町長の家の前で「彼ら」の姿をみかけた。青年と少女と犬と、なぜか少年が一人、旅の仲間に加わっているようだった。
少女は丁寧に老人に頭を下げていた。身分だけでいえば、彼女は最も高貴な者の一人といっても過言ではない。なのにもかかわらず、城の中でも、そして城の外でも、彼女の姿勢は変わることはないのだな……と男は思った。
決して尊大に振舞うことも、身分をひけらかすこともなく、それでいて、そこはかとなく漂う「品」。それは意識して出来るものではない。
騎士団は彼女を評議会から離し、「帝王学」を学ぶ機会を与えなかった。評議会としては、傀儡にするには愚鈍な方が望ましいという思いもあったのか、軟禁状態であるにもかかわらず、黙認していた。
もう一人の皇帝候補を擁立する騎士団にとっても、それは好都合だったに違いない。
しかし彼女は閉じられた世界の中で、率先して書物に目を通し、ただ怠惰に日々を送ることはしなかった。
おごりのないその「心」。他者へのいつくしみと労り……汚れを知らないきれいな心。
それは同時に危うさも抱えている。
デイドン砦の一件は、すでに男の耳に入っていた。目撃者も多く、追われる身であることを失念しているかのような「浅はか」な行動だ。
「予想を超えてくれちゃってるわ。まったく……」
次から次へと面倒なことに首を突っ込んでばかりいる……そう見えるのだが、同時に面白いとも男は思った。
昨晩この街に立ち寄った時、今は接触すべきではないと判断し街を出たが、そのまま残っていれば面白いものが見られたかもしれない――その思いは街をふらりと歩いてみてさらに強まった。
少女が奇跡を起こした……街はその話題でもちきりだったからだ。
「いやはや、最初はダメかと思ったんだよ。男の子が何か薬のようなものを根元にまいていたんだがね……量が少ないのか調合を間違えたのか」
「すごいのー! ピンクのおねえちゃんがね、お祈りしたらね、ハルルの樹がふぁああーーっっって」
「季節はずれもいいとこさ。枯れかけてた樹が満開になるんだから。もうこりゃ、奇跡としかいいようがないねぇ」
「クリティア人の仲間に聞いても、おそらくこのような光景を目にしたことはないでしょう。この街に来て、今はよかったと思っています」
人々は口ぐちに奇跡の一瞬を語った。魔物に襲われ辛い思いをした分、この喜びを口にしたくてたまらないのだろう。
男はこの街の結界魔導器であるハルルの樹の根元に立った。
「こりゃ、すげぇなー」
天まで届きそうなほど高く、どっしりと太い幹。広がる枝には淡いピンク色の花が咲き誇り、ゆるやかな風に乗って街じゅうにその花びらを落としている。
とくに根元は、じゅうたんのように花びらがつもっていた。これだけの花びら……いったい何枚あるのだろう。想像もつかない。
「ま、数えようとする変人もいないか」
男がたたずんでいると、次から次へと町の人間や、旅人たちが、ハルルの樹を眺めにきた。みな驚嘆し、その美しさに感激している。そして、樹の復活を目の当たりにした人々は、より一層感動の度合いが深いように見てとれた。
耳で聞くのと、実際に目にするのでは印象は大きく異なるはずだ。少女が起こした奇跡の一瞬は、何度でも人々の口にのぼり、語り継がれることになるかもしれない。
皇帝の血筋に連なるものには「ある力」があるという。一族の中でもエステリーゼ姫はとくにその力が強かった。だからこそ評議会は彼女を担ぎ出したという。
この「奇跡」が、その力に由来するものであったなら……騎士団長への報告事項がまた一つ増えたかもしれない。
男は着物をふわりとなびかせ、ハルルの樹に背を向けた。諜報活動も大切だが、今は急ぎの用がある。
ふっと視界のすみに黒い影が映った。すっと茂みに身を隠し、男は様子をうかがう。黒い影は数人。赤色の射光グラスをはめ、そろいの黒い服に身を包んでいる。姿だけみれば、城に侵入した者たちと一致する。
(やはり海凶の爪か……)
五大ギルドの一つ「海凶の爪(リヴァイアサンのつめ)」は表向きは武器商人ということになっていた。しかし、黒い噂が絶えないギルドでもある。その内容から「死の商人」と呼ばれることも多かった。
風下にいるせいで、低い囁きが風にのってわずかに聞こえてくる。
「……よく分からない命令だ……。騎士団に追いつかれたら奴らを襲うふりをして、騎士団ともめろとは……」
「今は城に戻ってほしくないお方がいるのだろう……」
「しかし日中に街中でことを起こすことになったらどうする……城の一件もある。騎士団にこれ以上目をつけられるのは………」
「……首領の命令だ……何かお考えがあるのだ……」
風が変わり、声は届かなくなった。茂みに身を隠したまま、男は無精髭の生えたあごに手を当てた。
脳裏に赤い鎧を身にまとった偉丈夫の姿が浮かぶ。彼は、周囲から懐刀と呼ばれる「隊長首席」にすら全てを語ってはくれない。
所詮は彼の「道具」にしかすぎないからだろう……男は自嘲的な笑みを浮かべる。分かり切ったことだった。そのために道化でも何でも、彼の望むままにこの10年を過ごしてきたのだ。
その間、彼の命令で「二つの世界」を行き来し、双方で尊敬と称賛を集めることもあった。
(すべてはまやかしだ。誤解という名の)
空っぽなのだから。自分は。
人の気配がないことを確認して、男は茂みから出た。軽く土埃をはらい、何事もなかったかのように坂道を降りていく。
フレンはノール港へ向かうだろう。そうなればエステリーゼ姫もそこへ向かうに違いない。そして、ローウェルはコア泥棒がどこにいるにせよ、彼女を放っておくことは出来ないはずだ。
「俺様も港へと行ってみますか」
そこで彼らと接触してみるのも悪くない。男の顔には先ほどとは違う笑みが浮かんでいた。
ソディアに指示を出し、先にノール港へと向かわせたあと、フレンはシャイコス遺跡を調査した。元々は別動隊にまかせるつもりだったが、事情が変わったのだ。
ウィチルの案内のもと調べてみると、本来ならば一般に知られていないはずの地下遺跡まで盗掘者によって荒らされた跡があった。魔導士を装った怪しげな輩もみかけたが、あと一歩のところで逃がしてしまった。
しかし自ら足を運ぶことで、得ることもあった。一味のものとおぼしき者を捕えることができたからだ。その者は下っぱであまり詳しい事情を知らないようだったが、それでも彼らをとりしきる者が「トリム港」に居るということは分かった。
ノールとトリム。二つで一つの町。
符号がぴたりと一致する。
ノール港を目指し急ぎたいところではあるが、これから花の街ハルルに向かわねばならない。部下の一人から、街に奇跡が起こり結界が復活したと聞いたからだ。一体何があの街で起こったのか……フレンの脳裏に可憐な姫君と黒豹のような友の姿が浮かぶ。
駐屯地のテントの中で、フレンは今一度、シュヴァーンからの書簡を手にした。
封筒の中にはもう一枚、四つ折りにされた紙が入っていた。ゆっくりとそれを開く。
「ユーリ……君が帝都を離れたことは嬉しいが……」
絵心のない者が描いたのか子供の落書きのような顔が大きく描かれている。添えられた名前はユーリ・ローウェル。
手配書だった。
帝都に残した部下から、早馬で知らせも届いていた。城内に暗殺者が現れたこと、一部はフレンの部屋にも侵入したこと、混乱に乗じ、投獄されていたローウェルが姫君を連れて脱獄したこと。
(なぜ君が彼女と一緒に……)
ユーリが女性を誘拐するような輩でないことはフレンにも分かっていた。何か事情があったに違いない。
エステリーゼ姫が「フレンに身の危険が迫っていることを伝えたい」と強く望んでいたことも報告に上がっている。
信じたくはないが、それが関係しているのだろうか。
懸賞金の額は5000ガルド、皇帝候補の誘拐にしては低すぎる額である。おそらく姫君の一件はまだ極秘事項に違いない。
(それにしても……エステリーゼ様は刺客のことをどこで耳にしたんだ?)
フレンは自分の身に危険が迫っていることを知っていた。アレクセイ騎士団長から「探し物」の一件を命じられてから、何度かそのような輩に襲われたからだ。だが、その事実を知るものは極めて少ないはずだった。それがよりにもよって、姫君の耳に入るとは……。
(考えたくはないが、騎士団の中に内通者がいるのかもしれない)
でなければ、城内に暗殺者がやすやすと侵入できるはずがない。裏で誰かが手引きしたのだ。その者が評議会とつながっているとすれば、むしろエステリーゼ姫の方が危険な状態にあるのではないか……フレンの眉間に深い皺が刻まれる。
ありえない話ではない。ヨーデル殿下を拉致した評議会が次に行うのはエステリーゼ姫との接触だろう。彼らはなんとしてでも彼女を取り込み、皇帝候補ではなく時期皇帝にしたいはずなのだ。
それを考えれば、今は城内に居るより魔物が跋扈する外の世界の方が、暗殺者の手に落ちる可能性も低く安全かもしれない。
ユーリが側についているのだから。
もう一度手配書に眼を通す。ユーリの「世界」が帝都の外に向かうことは賛成だ。しかし、犯罪者として指名手配されることがいいはずがない。何より彼が友と知れば、真面目で規律を重んじるソディアはよしとしないだろう。
(彼と話したいことは山ほどあるが……)
エステリーゼ姫からもこの一件の詳しい事情をきかねばなるまい。なぜ2人はともに帝都を出ることになったのか、当人しか知らぬ事情もあるだろう。
(ハルルで出会えればいいが)
部下の話では、デイドン砦でそれらしき男女が逃げ遅れた人々を救いだしたという。ユーリの旅の目的は詳しくは知らないが、エステリーゼ姫がフレンに会いたいのであれば、必然的にハルルを目指すはずだ。
しかし、仮にあの街で出会えなかったとしても彼らを待つ時間はなかった。すでにかなりの時間をロスしている。「探し物」のためにもノール港へ急がねばならなかった。
(早く追いついてこい、ユーリ)
フレンは紙を取り出し、ペンを走らせた。
--------------------------------------
※読まなくてもいい話※
すみません、おっさん小説とかいいながら、半分フレン小説でした…。アレ?
リタっちを仲間にしてからハルルの町へ行くと、フレンがユーリに置手紙をしてるんです。そこには「暗殺者には気をつけろ」とあるんですけど、けっこう行動とか謎なんですよね。フレンも、リヴァイアサンの爪も。なので勝手に捏造。すみませんー。
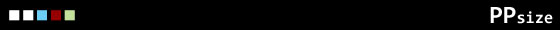
2010. 5.9.
|