報告を受けたと同時に、地下から鈍い振動が伝わってきた。
「シュヴァーンは敗れたか…」
誰ともなくつぶやいた言葉は、報告に上がった騎士の耳にも近衛の者たちの耳にも届かないほどかすかだった。
あらかじめ分かっていたことだった。
だのに足から体へと伝わった揺れが、彼の重く固い心にまで届き、僅かな揺らぎを与えている。
バクティオン神殿の半開きの扉から外の明かりがもれていた。
アレクセイは足を止めた。
もともとはデュークを生き埋めにするはずだった。だが予定が狂った。
デュークは現れず、代わりに彼らが追ってきた。
イエガーが素人相手に遅れを取るとは思い難く、また短時間で追ってきたところをみると、あの男は命令に反したばかりか抹殺すべき敵に情報を流したのかもしれない。
アレクセイの眉間に深い皺が刻まれる。
イエガーは全く本心を表に出さなかった。
それはシュヴァーンも同じだが、シュヴァーンは裏で何か画策するという性格ではなかった。レイヴンとしてドンの腹心となっても、彼は必ずアレクセイの元に戻り報告を上げた。レイヴンとして過ごす時間の方が長くなっても、それは変わらなかった。
何の感情も持たず、ただ黙々と与えられた任務をこなしている…アレクセイにはそう見えた。
同じ道具でもイエガーはアレクセイの知らない所で様々な画策を行っているふしがあった。今回に限らず、命令を遂行して いるようでいながら、意図的に怠っていることも幾度かあった。
イエガーには、例えどこかで歪みが生じていたとしても、明らかに意志があった。
(私を裏切るのならば、それ相応の報いを受けねばならん)
だが、シュヴァーンですら敗れたとあらば、イエガーもまた、彼らの強さの前に膝を折ったのかもしれない。
(素人に毛が生えた程度だと思っていたが……)
姫君を手に入れたあと、アレクセイはシュヴァーンから彼らにまつわる報告を受けていた。
決して侮ってはならない相手だと。
その強さは本物だと。
側でずっと「仲間」の仮面を被って監視してきた者の言葉は大袈裟でも誇張でもないだろう。
だからこそ、シュヴァーンに彼らを殺すよう命じたのだ。
油断のならない敵であるなら、手の内を知りつくした者に戦わせる……それは妥当な判断であるはずだった。そもそも、本気のシュヴァーンに彼らが勝つ確率など万に一つもない――場数も経験も技量もすべてにおいて勝っているのだから。
だが、現実は違っていた。
最深部への入口が爆破されたということは、すなわちシュヴァーンが負けたということだった。
残してきた親衛隊には、予め宙の戒典を持つ者たちの抹殺を指示しておいた。シュヴァーンが負けた時、最深部を爆破しろと。それで地下全体が崩落し、騎士たちにまで被害が及んだとしても、アレクセイにとってはどうでもいいことだった。
負けた時点でシュヴァーンは死ぬ。
それはアレクセイにとって『確信』だった。
彼らを殺すことを命じた時、シュヴァーンは表情一つ変えなかった。異を唱えることもなかった。
むしろこれで全てが終わる…冷たく暗い碧色の瞳に一瞬だが安堵にも似た感情が浮かんだようにアレクセイには見えた。
ようやく死に場所を見つけた……そんな風にも取れる眼差しだった。
事実、確実に抹殺するために親衛隊を与えたのに、シュヴァーンは隊を退かせた。たった一人であの場に残り、偽りの姿から本来の姿に戻り、彼らと対峙した。
アレクセイは騎士団長として隊長首席に加勢するよう、改めて親衛隊に命令することも可能だった。
だが、アレクセイはそれをしなかった。
シュヴァーンは固辞するだろう。それもまた確信だった。
己の命を懸けて戦う――すなわち、心臓魔導器の力を使うつもりなのだ――漠然とそう感じた。心臓魔導器の力を使うことは危険を伴う。大きな力を得られる見返りに体にかかる負担が大きすぎるのだ。
使い方次第では命にかかわることをシュヴァーンはよく知っていた。それでも、あえてその力を使うというなら、最初からシュヴァーンは死ぬつもりだったに違いない。
アレクセイの脳裏に、黒髪の美しい若者の姿が浮かんだ。若さが時に青さとなり、苛烈な方法も厭わない強さがあつた。これ以上ない程に、姫君を連れたまま上手く立ち回ってくれたばかりか、目障りな執政官を一人消してくれた。
ユーリ・ローウェル。
やさ男ともとれる顔立ちに反して、抜き身の刃のような男。
あの若者は裏切り者を決して許しはしないだろう。
たとえ死闘の末にシュヴァーンが戦意を喪失したとしても、彼は間違いなくとどめを刺すに違いない。
つい今しがたの出来事をアレクセイは思い起こした。
自分の手の中にある姫君を見た時の彼らの顔。憎悪と怒りがないまぜになった顔。
アレクセイが思っている以上に、あの姫君は彼らにとって大切な存在になっているようだった。だからこそ、姿を偽り、名前を隠し、裏切り、姫君を拉致した者にも、同様の怒りと憎しみを覚えるに違いない。
あの若者に限って、シュヴァーンを許す…ましてや再び仲間に引き入れることなど、ありはしない。
そもそも10年もの間、死を望み続けたシュヴァーンに生きる力を与えることなど、もう誰にも出来はしないのだ。
アレクセイは目を伏せた。
この私ですら出来なかったのだから……。
シュヴァーンは死んだ。
もう二度と会うこともない。
アレクセイは再び歩き出した。
バクティオン神殿から外へ出ると、じめじめとした地下とは対照的に、抜けるような青空が広がっていた。ゆるい風の中、木々が波のように揺れている。
どこまでも美しい世界。
穏やかで清んだ世界。
だがアレクセイの目には、それが嘲笑に映った。世界からの嘲り。
「すべてはまやかし。この歪んだ世界を統べることができるのは私だけだ」
その声に揺るぎはもう無かった。
--------------------------------------
※読まなくてもいい話※
アレクセイの言葉遣いはキレイな気がします。なんとなく。なので、ユーリたちのことは「彼ら」というふうに表記しました。「奴ら」ではなく「彼ら」。そして、タイトルにもありますが、アレクセイにとってはユーリこそが誤算だったのかな?と。
本文中にアレクセイがユーリを評していろいろ思っていますが、アレクセイはそういうふうに思っていたけど、彼の想像を遙かに超えた存在だったんだと思います。ユーリは。さすが主人公!
それにしても、どうしてアレクセイが好きなのか、今だに自分が分からない。
アレクセイにどこか「哀しさ」を感じるからかもです。
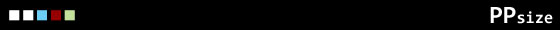
2011. 02.11.
|