繁みの陰に隠れながら、少年は様子をうかがっていた。
「何度見てもおっきな屋敷だよね。評議会のお役人ってそんなに偉いの?」
少年が疑問を抱くほど、執政官の館は大きく堂々とした佇まいだった。汚れ一つない美しい壁、窓や扉を彩る細部まで計算され尽くした装飾、贅をこらした造りであることは一目瞭然だ。
独り言のような問いかけに、ハルルの花びら色の髪をした少女…エステリーゼが丁寧に答えている。
「評議会は皇帝を政治面で補佐する機関であり、貴族の有力者によって構成されている、です」
「言わば、皇帝の代理人ってわけね」
魔導士風の少女がざっくりとまとめた答えに、少年は「へえ、そうなんだ」と素直に感心している。
その様子をざんばら髪の男がやや離れた物陰から伺っていた。
男の思ったとおり、彼らはこの街の惨状を目の当たりにして、見て見ぬふりなどできはしなかった。
悪名高い執政官が放った魔物をわざわざ探しだし、危険を犯して戦った。そればかりでなく、苦労して手に入れた魔物のツノを困っている市民に簡単に与えてしまった。本来の計画では執政官に謁見するために必要だったはずのものをだ。
エステリーゼが言っていた。「最初からこうするつもりだったのですね」と。
ローウェルはおそらく、思った以上に情の深い男なのだろう。
それにしても…と男は口の中でつぶやいた。
少し見ない間に、ローウェル一行はまた一人増えたようだった。ハルルでは少年、今度は少女と加わるのは子どもばかりである。
新たに加わった茶髪の少女はアスピオの魔導士にちがいない。
帝国の管理下にあるあの街から、指名手配犯の仲間に加わる物好きはそういないはずだが…と男は顎に手を当てた。
変人で名高い魔導士はひとり知っている。以前、アレクセイの命によりアスピオまで会いに行ったことがあるからだ。当時から魔導器研究において天才の名をほしいままにし、年齢にそぐわぬ高度な術式や論理を展開していた。人嫌いで気難しいとの噂が帝都まで届いており、噂に違わずけんもほろろに追い返された記憶がある。
年格好、性別、顔立ちなど一致する点ばかりだが、彼女がアスピオの外をほいほいと出歩くことは考えにくい。
(旅を続けるエステリーゼ姫……ギルドの少年に魔導士少女…ローウェルが子どもや女性に人気があるのは本当のようだな)
長い黒髪や、一見女性かと見紛うばかりの整った顔立ち、すらりとした痩身は別の意味でも女性に人気がありそうだ。
男は唇の端を上げた。
いや容姿よりもむしろ、彼の豪胆さや男気こそが、多くの者を惹き付けてやまない魅力なのかもしれない。
男は少しずつ彼らとの距離をつめた。
誰一人、男の気配に気づいたものはいない。ローウェルでさえも。
己の気配を絶つことなど、男には造作のないことだった。そうでなければ、今、こうして生きてはいない。
(まてよ、ひとり気づいてるか)
男は目を細めた。
ローウェルのかたわらに鋭い目をした一匹の犬が居た。帝都を出た時からずっと、ローウェルとともに居た犬だ。その彼がかすかに鼻を鳴らしている。
男の視線に気づいたのだろう、目があった。
足を止め、男は様子をうかがった。吠えられるだけならまだしも、向かってこられたらやっかいな相手だ。
だが、犬は長いあくびを一つしただけだった。
男は感心した。賢い犬だと思った。
気配に気づいていながらあえて無視するのは、男が敵意や害意をもっていないと判断したからだ。
いちいち相手をするのも無駄だといわんばかりに、悠然と構えている。
(まったく大したわんこだね)
男は浮かんだ笑みをふっとおさめた。
もし、男が明確な殺意を抱いて彼らの前に現れたなら、あの犬は間違いなく吠えたはずだ。それがどのような場所でも、どのような姿であっても、必ず吠えて主人に知らせるだろう。
必ず……。
「どうやって入るの?」
魔導士少女は少々気が短いようだった。
男はさらに距離をつめた。まだ一行は気づかない。
エステリーゼが小首をかしげた。
「裏口はどうです?」
「残念、外壁に囲まれてて、あそこを通らにゃ入れんのよね」
「……っ!?」
声をかけて初めて、彼らは気づいたようだった。見知らぬ男が突然会話に割り込んできたのだ。最初の驚きが過ぎ去るとギルドの少年も魔導士少女も怪訝を通り越して不審になった。胡散臭そうに男をじろじろと見ている。
エステリーゼの目が丸く見開かれた。
(これは気づかれたか…?)
城内では幾度か謁見したことがある。かなり以前のことだが、簡単な会話も交わした。
「こんなとこで叫んだら見つかっちゃうよ、お嬢さん」
唇に人さし指をあて、静かにしよーね?と片目をつむる。あくまでも軽い口調、軽いものごし。
エステリーゼはまばたきを一つ、二つした。
「えっと、失礼ですが、どちら様です?」
きょとんと見つめる彼女の目に嘘はない。
男はにこにこと笑ってみせた。含みたっぷりに言い放つ。
「な〜に、そっちのかっこいい兄ちゃんとちょっとした仲なのよ。な?」
「いや、違うから、ほっとけ」
間をおかずローウェルが否定する。そっけない口調から、関わりたくないと思っているのは明らかだった。
ここまでは男の予想通り。彼らの前に姿をさらし会話をする……ローウェル一行内での男の立ち位置が決まる重要な第一歩だ。
「おいおい、ひどいじゃないの。お城の牢屋で仲良くしたじゃない、ユーリ・ローウェル君よぉ」
ことさら大仰に言った言葉にローウェルは反応した。眼差しに剣が宿る。
「ん? 名乗った覚えはねぇぞ」
ユーリ・ローウェルは凡庸な若者ではない。これはやりすぎたか……と男はすかさず手配書をちらつかせた。フレン・シーフォに送ったものと同じものだ。
「ユーリは有名人だからね」
少年が納得顔でうんうんと頷いている。
どうもこの一行は緊張感が薄い。似顔絵入りで指名手配されているというのに、ことの重大さを忘れているようだ。だが…と男は考え直した。そのくらいの方が、自分にとっては都合がよいだろう。
「で、おじさんの名前は?」
ローウェルの知り合いと受け取ったのか、少年は男に興味を抱いたようだった。
「ん? そうだな……」
今後もちょくちょくこの姿で会うことになるだろう。
「とりあえずレイヴンで」
「とりあえずって……どんだけふざけたやつなのよ」
苛立ちもあらわに魔導士少女はレイヴンをにらみつけた。ふざけたもの言いが余程お気に召さなかったのか、「不審」から「戦闘態勢」に移ろうかという勢いだ。
少女とは対照的に、ローウェルはいちいちからむのも面倒らしい。
「んじゃ、レイヴンさん、達者で暮らせよ」
これ以上関わりたくないのだろう、手をひらひらと振っている。
「つれないこと言わないの。屋敷に入りたいんでしょ? ま、おっさんに任せときなって」
上手くいくかは運次第…門を守る傭兵が単純な奴らであることが前提だが、たとえ失敗しても他に方法はいくらでもある。
ローウェル一行の返答も待たず、レイヴンはひょいひょいっと門まで走っていった。
続きます。
--------------------------------------
※読まなくてもいい話※
会話部分はゲーム本編通りですが、相変わらず捏造です。
基本的にはPS3版をベースに、このお話を続けていくよていです。とにかく、カルボクラムからヘリオードのあたりがすごく書きたくてしょうがないので、がんばって早く到達したいです。遅筆なのでかなり時間はかかりそうですが…。。
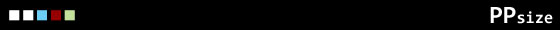
2010. 12.1.
|