港街カプワ・ノールは、曇天もあいまって淀んだ空気に満ちていた。街を行く人々の顔は、まるで空を映したかのように薄暗く覇気がない。口数はみな一様に少なく、眼差しに怯えと疲労がにじむ者も多く見てとれた。
その元凶の一つともいえるだろう、ギルドの者と覚しき風体の者たちがそこかしこにたむろっていた。しかも、ギルドユニオンの中でも、穏健とは言い難い部類に属する者たちだ。
「あいつら、間違いなく紅の絆傭兵団(ブラッドアライアンス)よねぇ……」
派手な色の着物にざんばら髪。見るからに胡散臭い男は、無精髭の生えた顎に手をあて、誰ともなくつぶやいた。
男がこの町に入ってから、既に数刻が過ぎていた。石造りの民家の二階に宿を取り、窓辺で頬杖をついたまま通りを眺めている。
緩んだ表情も、まとう空気も、何もかもがくだけすぎていて、一見するとぼーっとしているようにしか見えない。
誰一人として、この男が何を眺め、何を思っているのかなど気にも留めないだろう。
それを「知る」からこそ、男は体を動かすことなく、視線だけを巡らせて町の隅々に目を走らせていた。
ふと男のまゆがあがる。
裏通りの物陰に黒ずくめの男たちが数人固まっているのが見えた。
(奴ら……海凶の爪か……?)
ユーリ・ローウェルが姫君を連れて脱獄したまさにあの夜、城内に潜入した謎の暗殺集団。応戦した部下の報告にあった彼らの風貌と、今、男が目にしている者たちの風貌は酷似していた。
彼らは何かひそひそと情報交換をしているようだったが、すぐに散り散りになり通りの陰に姿を消した。
「執政官どのの交友関係を甘く見すぎてたかねぇ」
今にも落ちてきそうな重たい雲の下ならば、裏の仕事もしやすいのかもしれない。
何か他に妙な動きはないだろうかと、少しばかり窓から身を乗り出したその時――。
「やめてください、母が病気で倒れたんです。それはお医者様を呼ぶための……」
不意に女性の悲痛な声があがった。向かいの家の入口の戸が開いている。戸口から見える部屋の中は無惨に荒らされ、人相の悪い男が二人、そこから引き上げようとしているところだった。
「おいおいおい、さんざん滞納したあげくがそんな嘘かあ?」
「嘘ではありません、本当に…」
「だったらリブガロの角でも取りにいきゃあいいだろ」
「こんなはした金ためるよりは手っとり早いぜ?」
男たちはげらげらと哄笑している。
女性は唇をかみしめ、床を見つめた。リブガロは魔物の中でも体が大きく凶暴だ。結界の外に出ることすら一般市民にとっては多大な危険が伴うのに、そのような魔物と対峙するなど不可能に近かった。
笑いながら男たちは去り、残された女性はのろのろと立ち上がると、開け放たれた扉に手をかけた。
執政官が代わり、より帝国の威光が強くなったはずが、騎士ではなくならず者が税の取り立てをしている……それを目にしても、男の表情は変わらなかった。
なぜなら彼は、何度となく、トリムとノールを行き来し、その都度、この悲惨な状態を見てきたからだ。
「すまないが、話を聞かせてほしい」
真下から声がした。扉を閉じようとしていた女性が手を止める。
彼女の顔は再びこわばった。
「な……何のご用ですか」
声に怯えが走る。女性の前には二人の人影。
一人は魔道士の服に身を包んだ小柄な少年。もう一人は、騎士の鎧に身を包んだ女性だった。
「おやおや」
窓辺から様子をうかがっていた男は、身を屋内へとひっこめた。見つかっては困る相手だったからだ。
女性騎士は紛れもなく、フレン小隊の副官だった。隊長であるフレンの姿がどこにも見えないところを見ると、先発隊といったところか。
「騎士の姿で聞き込みねえ…」
一般市民にとって、騎士に対する印象はあまりよくないはずだ。帝国の威信をふりかざし、横柄で尊大な振る舞いをする者も少なくなく、また、税の厳しい徴収などで涙を流した者も多いだろう。
案の定、女性の顔には不安と緊張が走ったままだ。その彼女に騎士は何事か話しかけている。
先ほどまでとは違い、騎士も女性も声を落としているため、男のところまでは声が届かない。
だが、女性の表情には明らかな変化が生じていた。少しずつ警戒の色が薄れ、代わりにうったえかけるような強い思いが全身からあふれ出している。
騎士がさらに何事か問いかける横で、少年は紙にペンを走らせ一言一句聞き洩らしのないよう書き留めていた。フレン小隊の本体が到着するまでに出来る限りの情報を集め、取りまとめておくのだろう。
男は唇の端に笑みを浮かべ、窓辺から立ち上がった。
「なかなか、やるじゃない」
着物の裾をふわりとはためかせ、男は部屋から出ていった。
黒ずくめの男たちは、命令を伝えにきた仲間の一人に、低くささやくような声で問いかけた。
「ローウェルは確かに賞金首だが……奴を騎士団に突き出すわけでもあるまい」
「奴を襲う理由はなんだ」
仲間の反応に黒ずくめの男は声を荒げた。
「貴様ら、首領の命令に従わぬというのか」
今にも斬りかからんばかりの様子に、別の男がなだめに入る。
「そうは言わん。ただ、どこまでやればいいのかということだ」
「奴が逃げ出すか、もしくは死ぬまでだ」
首領の命令は、ローウェルが一人になったらそこを襲えというものだった。戦う者は何人でもかまわない。
「我らが集団でかかれば、ローウェルの奴、逃げる間もないだろう」
あまりに簡単な仕事である。難しく考える必要などなく、単純に殺せという意味ではないのか……男たちの半数以上が命令の意図を掴みかねていた。
その上、実行時期は出来るだけ早く。しかも宵闇に紛れてではなく、日中でもかまわないという。
真に暗殺を目的とするならば、このような計画は愚の骨頂だ。だが、彼らの首領はそのような愚策とは無縁の人物だ。それはみな知っていた。
「こちらが不利になれば、深追いはするなとのことだ。もしや、奴の技量を計るためではないか?」
一人がそうもらすと、もう一人がせせら笑った。
「賞金首とはいえ、所詮は素人にすぎん」
技量を図ることに何の意味があるというのか。
「大体、相手は一人だぞ?」
実戦経験もさほどあるように見えず、腕も細い。まさかそのような若造に遅れをとるはずがないだろう。
「確かにそうだ」
ローウェルには無惨で哀れな最期が訪れる……その場に居た全員がそれを信じて疑わなかった。
路地裏から斬撃の音が鳴り響く。乱れた呼吸音、剣が交わる悲鳴のような音。
深い傷を負いながらも多勢に無勢、ユーリ・ローウェルをあと一歩まで追いつめた黒ずくめの男たちだが、突如現れたフレン・シーフォによって一気に形勢が逆転した。ユーリとフレンの息のあった攻撃の前に、なすすべもなく攻撃を跳ね返され、そのまま積み上げられた木箱にたたきつけられる。
戦意を喪失したのか、それまで次から次へと襲いかかってきたはずの暗殺者たちは、煙のように失せていった。
「ふう…マジで焦ったぜ」
額に落ちる黒髪を軽くかき上げ、ユーリは汗をぬぐった。
「さて」
乱れた呼吸を整え、フレンは敵に向けていたはずの剣をユーリに向けて降りおろした。
「ちょ、おまえ、何しやがる!!」
反射的に剣で受けとめたが、フレンは力をゆるめない。互いの刃先がぎりぎりと震える。
「ユーリが結界の外へ旅立ってくれたことは嬉しく思っている」
はじかれたように離れた2人だったが、すぐにフレンは剣を大きく振りかざし、再度ユーリに向かってきた。数度フレンの振りをかわしつつ後退し、彼の剣戟を自身の武器で受けとめる。
「ならもっと喜べよ。剣なんか振り回さないで」
「これを見て素直に喜ぶ気が失せた」
フレンはユーリに向けていた剣を壁に付き立てた。そこには雨に濡れた手配書が掲示されている。
「あ、10,000ガルドに上がった。やり」
フレンのまなじりが吊り上がる。指名手配されていることにまったく危機感がないばかりか、懸賞金が上がったことを喜ぶとは一体どういうことなのか。
「騎士団を辞めたのは犯罪者になるためではないだろう」
「いろいろ事情があったんだよ」
やれやれと言わんばかりにユーリは右手を振る。
何かしら事情があった……それが分からないほどフレンも愚かではない。だが問題はそこではない。
「事情があったとしても罪は罪だ」
理由は免罪符にはならない。そもそも罪を犯して収監されていた者が、脱獄をするなどあってはならないことだ。にもかかわらず、ユーリには罪の意識がまるでない。
フレンにとって、そこが一番の問題だった。
「ったく、相変わらず、頭の固いやつだな……あっ」
ぼやくユーリは、不意に一段高くなった通りを見上げた。見知った姿がそこにいた。
「ユーリ、さっきそこで何か事件があったようですけど……」
現れたのは、青年たちとそう年の変わらない少女、エステリーゼだった。
彼らの様子を、紫色の羽織の男は、建物の三階から見降ろしていた。宿をとった建物とは別の棟だ。
彼らのやりとりを聞くかぎり、報告書にあったローウェルとフレンが同じ時期に騎士団に入団し、旧知の間柄であるというのは、紛れもない事実だろう。
フレンはともかく、ローウェルの戦う姿を見るのはこれが初めてだった。騎士団に居たはずだが、彼の剣は、かなり奔放で自由だった。騎士団の剣術試験であれば、点がつくどころかマイナスになりかねない。だがその分、非常に実戦向きでもあった。
ローウェルはこれまで何度も追手を出し抜き、そして凶暴な魔物をもろともせず、ここまでたどり着いた。
今もまた、海凶の爪とおぼしき男たちの攻撃を見事な腕で切り抜けようとした。ローウェルのような下町の若者を、わざわざ人数をかけて襲うことに何の意味があるのか定かではないが、一つだけ確かなことがある。
彼らにとって、ローウェルの強さは相当な誤算だったに違いない。
(さて、これからどうなるかね?)
フレンと出会ったことで、エステリーゼ姫はごく自然な形で騎士団が預かり受け、頃合いを見計らって帝都にお戻りいただくことになるだろう。
脳裏に騎士団長の顔が浮かぶ。図らずとも彼の望んだ通りの結果が生まれようとしている。
だがこの町の窮状を、ローウェルも姫君も、見て見ぬふりなど出来るはずがない。これまでもデイドン砦で決死の救出を試み、ハルルでは力を失った結界を元通りにしてしまった2人だ。
ここでも彼らは必ず何か事を起こす。
それは確信。
「俺様も便乗させてもらいますかね」
窓の下では、エステリーゼ姫がフレンを目にするやいなや、抱きつきそうな勢いで身を案じている。そのまま、彼女を連れて立ち去るフレン。彼はこれから、旅の一部始終を彼女の口から確認するに違いない。
窓から離れると、男はけだるそうにのびを一つした。空き室に不法に侵入していたのだが、もうここに用はない。
ざんばら髪を軽く揺らしながら、彼は自分の宿へと戻っていった。
--------------------------------------
※読まなくてもいい話※
もうずっと捏造ばっかりですね(笑)
おっさんが、ノール港でユーリたちの目の前に現れる時、なんか、タイミング良すぎなとこがあったので、あらかじめユーリたちの動きを監視しつつ、彼らを利用したのかな?と勝手に想像して書きました。レイヴンは、聖核を探してラゴウのとこにいたとか言ってますが、そこにヨーデル殿下が居たことを考えると、これも彼の口にした嘘の一つかな?とも思ったり。
フレンはユーリが帝都を出たことを知っている……だからこそハルルで手紙を残したりしてたんですが、ということは、最初からエステルと旅してたこととか、脱獄したこととか全て報告を受けて知っていたんだろうと思いました。だから、単純にユーリが賞金首になったことに怒り心頭なわけではなく、それも含めて、いろいろな思いがあったのかな?なんて。
あと、海凶の爪がなんでユーリを襲うのか、よくわかんなかったのでそこも捏造。この連続小説を最初から読んでいらっしゃる方には、なんとなく伝わったらいいなと思います。
あ、あとお気づきだと思いますが、ユーリとフレンの会話部分は本編と同じにしてあります。念のため(笑)
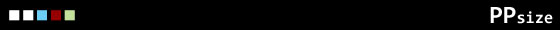
2010. 7.11.
|