「ローウェルは帝都から出たか…」
執務室にはアレクセイとシュヴァーンの二人だけだった。
脱獄と姫君拉致、赤目の侵入者たち…
夜を徹しての任務にもかかわらず、アレクセイの顔に疲れの色は見られない。
親衛隊や各小隊長から上がってきた報告をとりまとめ、それを評議会へ報告するために、美しい筆跡で書面をしたためている。
「エステリーゼ様もご一緒とのことです」
シュヴァーンはルブラン小隊長からの報告を騎士団長に伝えた。
下町まで追ったが、住民の妨害に合い、とり逃したこと。下級騎士二人が昏倒したこと。エステリーゼがユーリとともに帝都を後にしたこと。
アレクセイは手を止めた。
「ローウェルはなかなかおもしろい人物のようだな」
彼が座る机の上には、ユーリにまつわる報告書が束になって置かれていた。ユーリがまだ騎士見習いだった頃の成績表から、退団したあとに犯した山のような軽犯罪まで。
(あの短時間に、もう調べたのか)
顔には出さなかったが、シュヴァーンは心の中で唸った。
アレクセイは何事においても迅速だった。それは昔から変わらない。
策を張り巡らし、先手を打ち、この10年間、評議会が付け入る隙を中々与えなかった。
評議会側が騎士団に対抗して擁立したエステリーゼでさえ、アレクセイは自らの監視下に置き、帝王学を学ばせることもないまま軟禁状態にした。
痺れを切らした評議会が、ついにヨーデルの拉致などという暴挙にでねばならぬほどに、アレクセイの手腕は抜きん出ていたのだ。
そのアレクセイが、ユーリに興味を抱いている。それはシュヴァーンにも分かった。
アレクセイは唇の端に薄い笑みを貼り付けたまま、シュヴァーンに向かって束を放った。
「ローウェルはどの程度、時間稼ぎをしてくれるだろうな?」
新しい手駒を見つけた喜び… シュヴァーンの目に、アレクセイの表情はそう映った。
受け取った報告書の束を、シュヴァーンはきちんと揃えてから机の端に置いた。後で文官に返さねばならない。
「城から出たことのない姫様が同行しています。身軽というには程遠く、逃亡するにも徒歩になるでしょう」
「馬で追えばすぐ…か」
それではつまらんな…表情がそう語っている。
「ローウェルと姫様は我が隊のルブラン小隊に追わせるつもりです」
「ほう……ルブラン小隊か」
アレクセイの真紅の瞳がシュヴァーンに問いかける。
「あの小隊は、出来損ない小隊とも言われているようだな。ローウェルの報告書内にも、別の小隊から指摘があったが」
「彼らは、多少不器用ではありますが、任務に対しては真面目です。私が追えといえば、地の果てまでも追っていくでしょう」
弁護とも取れる内容に、アレクセイはシュヴァーンの耳に手を伸ばした。シュヴァーンはすっと一歩退く。
アレクセイはふん、と笑った。
「あの青年なら、おまえの小隊につかまるはずはない、ローウェルは姫様とともに身を隠しながら逃げ続ける。評議会にも追っている最中だと言い訳も立つ。そういうことなのだろう?」
シュヴァーンは答えなかった。
「まあ、いい。昨夜の一連の騒ぎについては、私が全責任を負う。ヨーデル殿下の一件もあるからな。評議会には少しばかりいい気分で居させてやろう」
アレクセイは再び机の上の書面に目を落とし、ペンを走らせる。最後に自分の署名と捺印をし、アレクセイはペンを置いた。
「昨夜、死んだのは四名だったな?」
「キュモール隊のものが四名です。今現在、重体の騎士が一名で、予断を許さない状態にあります」
「なるほど、報告が一部上がってないのはそのせいか……。無駄とは思うが、キュモールにも報告書を上げさせろ。形だけでも整えねばならん」
シュヴァーンは騎士団長に深く一礼すると、ユーリの報告書の束を小脇に抱え、アレクセイに背を向けた。
「シュヴァーンよ」
アレクセイが声をかけた。
「フレン小隊に接触し、急ぎノール港へ向かうように伝えろ。内容は分かっているな?」
「分かっております」
もう一度一礼してから、扉を開ける。アレクセイの視線は感じない。再び別の書面に目を通しているのだろう。
退室してから、シュヴァーンは息を一つ吐いた。
再び「レイヴン」として動くことになるだろう。それまでにシュヴァーン隊の各小隊長に命令を出し、ルブランにはユーリを追わせねばならない。
今度の「隊長不在」の期間は長くなりそうな予感がする。漠然とそう思った。
人魔戦争から10年。
アレクセイの道具として、彼の手足となってこれまで動いてきた。
任務の中で、ドンのような傑出した素晴らしい人間と出会えたのに、最後には、アレクセイの命を選ぶ自分が居ることを、シュヴァーンは知っていた。
自分の命を握られているからだけではない。彼の命令を遂行しなければならないという強い義務感が、考える力を奪っているのだ。
この呪縛から解き放たれることなどありえない。今までもそうだし、これからもそうだろう。だが……。
黒髪の青年の顔が浮かんだ。
誰にも媚びず、屈せず、抜き身の刀のような鋭さをまとった男。
彼に鍵を渡したのは、気まぐれにすぎない。自分ではそう思っていたのに、アレクセイには嘘だと言われた。
何かが変化するのではないか、そんな期待を込めていたのだとしたら……。
シュヴァーンは低く笑った。
柄にもないことだ。何も変わることなど、ありはしない。
アレクセイの覇王の道に、目を閉じてついていくだけなのだから。
--------------------------------------
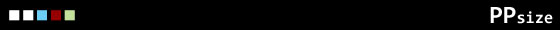
2009.08.25.
|